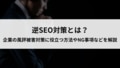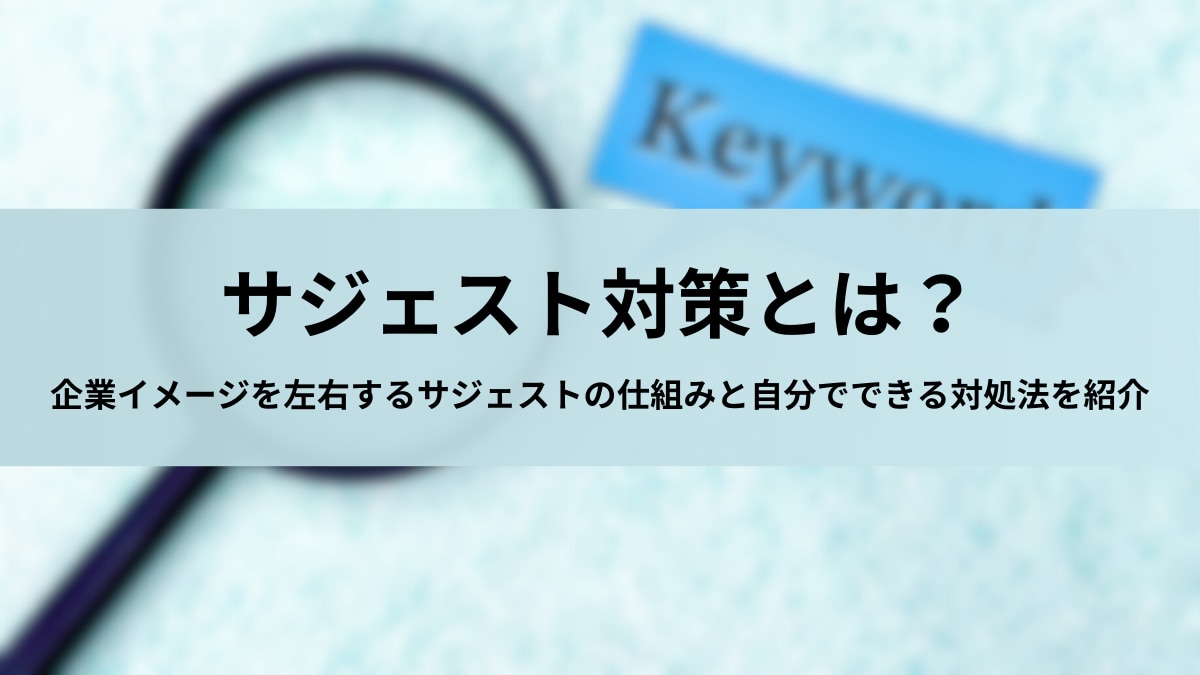
サジェスト対策とは?企業イメージを左右するサジェストの仕組みと自分でできる対処法を紹介
現代のインターネット社会では、検索エンジンは情報を探すための重要なツールです。しかし、膨大な情報の中から正確に欲しい情報を見つけることは時に困難です。そんな中、ユーザーの検索体験を向上させる検索エンジンの機能として「サジェスト」があります。
この記事では、サジェストの仕組みや企業におけるその重要性、そして対策方法について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.サジェストとは何か
- 2.サジェストの仕組み
- 2.1.Googleサジェストの仕組み
- 2.2.Yahoo!サジェストの仕組み
- 3.サジェストが企業に与える影響
- 4.ネガティブなサジェストへの対策方法
- 4.1.検索エンジンに削除申請する
- 4.2.弁護士に相談する
- 4.3.情報発信で相対的にネガティブな表示を減少させる
- 5.サジェスト対策に取り組む際に注意すべきこと
- 6.まとめ
サジェストとは何か
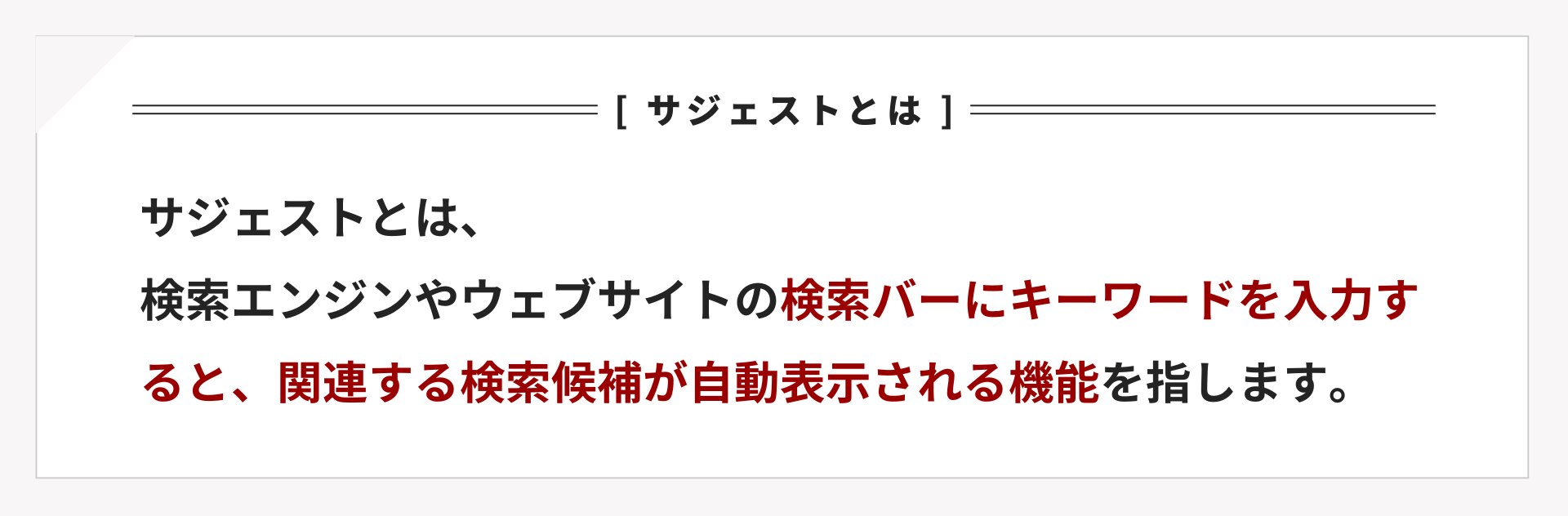
サジェストとは、検索エンジンやウェブサイトの検索バーにキーワードを入力すると、関連する検索候補が自動表示される機能を指します。
この機能は、「検索サジェスト」や「オートコンプリート」とも呼ばれます。サジェストで表示されている検索候補を選択し、検索するという方も多いのではないでしょうか。
サジェストの仕組み
日本国内で広く利用されている検索エンジンには、GoogleとYahoo!が代表的です。
令和4年版情報通信白書によると、国内ではGoogleの利用率が最も高く、スマートフォンではYahoo!も約20%のシェアを占めているとされています。
これらの検索エンジンのサジェスト機能をうまく活用することで、ウェブサイトの訪問者数を増やしたり、認知度を高めたりする効果が期待できます。
Googleサジェストの仕組み
Googleサジェストは、「予測入力候補」とも呼ばれ、Googleの自動システムが検索候補を生成することで、検索の入力を高速化する機能です。検索候補は検索頻度やトレンド、ユーザーの検索履歴など、さまざまなデータを基に作られています。
たとえば、特定のフレーズが多く検索されている場合、そのフレーズが優先的に表示されます。また、Googleでは地域や言語設定によってサジェストの内容が変わることがあり、ユーザーの居住地に関連したキーワードも反映されます。
Yahoo!サジェストの仕組み
Yahoo!サジェストは、「キーワード入力補助機能」と呼ばれ、基本的に入力したキーワードと一緒によく検索される複合キーワードが表示される仕組みになっています。検索地点によるサジェスト表示の違いはなく、全国どこで検索しても同じサジェストが表示されると言われています。
ただし、Yahoo! IDでログインしている状態では、パーソナライズ化されるため、過去のキーワード検索履歴などがサジェストの結果に反映されることがあります。
サジェストが企業に与える影響
サジェストの仕組みの次に考えるべきは、この機能が企業にどのような影響を与えるかです。サジェストは、ユーザーの検索体験を向上させるために設けられた機能ですが、その影響はユーザーだけとどまりません。ときには、検索結果に表示されるキーワードが、企業のブランドイメージに大きな影響を及ぼします。例えば、「おすすめ」や「安心」といったポジティブなキーワードが表示されれば、ブランドイメージの形成や向上にも繋がります。
一方で、企業名や商品名とともに「異物混入」や「情報漏洩」などのネガティブなキーワードが表示されると、ユーザーに悪い印象を与えるリスクが生じます。特に、私達はネガティブバイアスというポジティブな情報よりもネガティブな情報に注意を向けやすく、記憶にも残りやすい傾向を持っており、ネガティブな情報が与える影響は大きいと想定されています。
さらに、そのネガティブなサジェストのクリック数が増えるほど、検索結果の上位に表示されやすくなり、放置するとネット上での評判が悪化し、風評被害に発展する可能性もあります。
ネガティブなサジェストへの対策方法
このようなサジェストの考え方を押さえた上で、ネガティブなキーワードがサジェストに表示されたとき、具体的にどのような対策が取れるのでしょうか。大きくは、3つの方法での対策を講じることが出来ます。
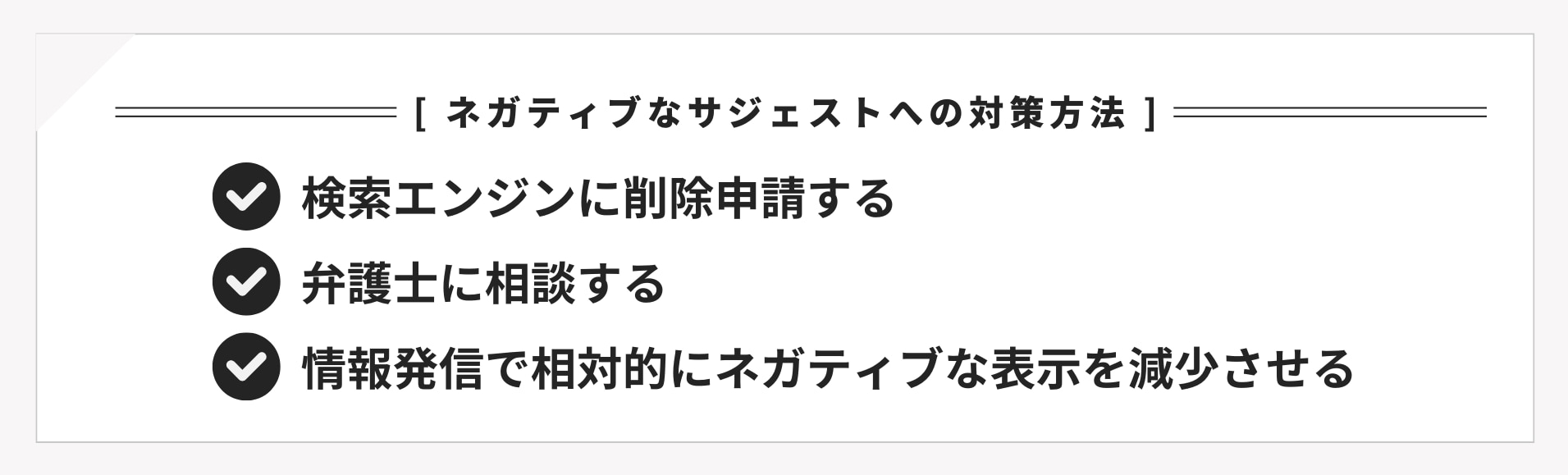
まずは、特定のネガティブなサジェストを削除するというアプローチの取り組みです。
検索エンジンに削除申請する
ネガティブなサジェストが企業のブランドイメージを損なう場合、自分で検索エンジンに削除申請を行うことができます。GoogleやYahoo!では、特定のサジェストを削除するための申請フォームを提供しており、以下から手続きが可能です。ただし、すべての申請が認められるわけではないため、注意が必要です。
Googleをはじめとする各検索エンジンは、公平性や中立性を重視しています。自分にとって「不都合な真実」でも、他者にとっては「有益な情報」と判断されることがあります。削除依頼を送信しても、必ずしもすべてが受け入れられるわけではないことを理解しておく必要があります。
Googleへの削除申請
Googleでは、以下の2つの窓口から削除申請ができます。自身の状況に応じた窓口を選び、必要な情報を入力して送信しましょう。
① 個人情報の削除申請
個人情報が検索結果に表示されている場合は、こちらの窓口から削除申請を行うことが可能です
② 問題のあるコンテンツの報告
個人情報以外で、法的な問題があるコンテンツについて報告する場合はこちらから行うことが可能です。
③ その他の報告
上記以外のキーワードに関してもGoogleにフィードバックを送ることができます。PCであれば、検索バーに検索キーワードを入力した際にサジェストの下に「不適切な検索候補の報告」というボタンが出てくるため、そこからフィードバックすることが可能です。
Yahoo!への削除申請
Yahoo!で検索結果の削除を希望する場合は、こちらから申請できます。
Yahoo! IDでログインし、必要な情報を入力して送信しましょう。申請が認められた場合、該当の検索結果が削除されます。
弁護士に相談する
検索エンジンへの削除申請に不安がある場合は、弁護士に相談することも一つの選択肢です。弁護士に相談することで、法的な観点から適切なアドバイスを受けることができ、申請手続きや削除可否についての見通しが得られます。
情報発信で相対的にネガティブな表示を減少させる
ここまでは、ネガティブな表現を狙い撃ちして、削除することで風評被害対策を講じる方法を説明してきました。
もう一つの取り組みが、企業などの情報発信やプロモーション活動を強化することで、ポジティブまたは、ニュートラルな情報を相対的に増加させ、ネガティブな情報を低減するというアプローチです。具体的な情報発信の方法として、以下のようなものがあります。
・プレスリリースの配信
新製品やサービスの発表や社会貢献活動の紹介を通じて、メディアへの露出を高めます。
・コンテンツによる情報発信
ブログや資料、動画などを通じて、利用者に役立つ情報を提供し、検索での表示回数を増やします。
・SNSによる情報発信
YouTubeやInstagramなどで製品情報や業界の話題を紹介し、利用者とのつながりを強めます。インフルエンサーとのコラボも効果的です。
・記事広告の掲載
対象に合ったウェブメディアに、製品やサービスを紹介する記事広告を掲載します。利用者の関心を引くような物語性を持たせ、自然に製品を紹介し、共感や興味を喚起します。
サジェスト対策に取り組む際に注意すべきこと
レピュテーションリスクマネジメントの観点でサジェスト対策に取り組む際に、留意すべきなのは、ユーザーの検索体験を向上させる検索エンジンの機能として「サジェスト」がある以上、ネガティブ情報がユーザーにとって有益と判断される場合は、サジェストに残り続ける可能性があります。
ネガティブなキーワードは確実に削除できるとは限らない
サジェスト対策だけでは企業に関するネガティブな評価を完全に解決することはできません。一時的にネガティブなキーワードを検索結果から目立たなくする効果があったとしても、問題自体を消すわけではありません。
また、前述のとおり、サジェストの削除申請が必ず成功するわけではありません。削除されない場合もあるため、企業はネガティブな評価となる原因にも積極的に対応し、信頼回復に努めることを推奨します。
「再出現」の可能性も考える
また、一度サジェストからキーワードが非表示になったとしても、永久に消えるわけではありません。サジェストは検索エンジンのアルゴリズムやユーザーの検索行動により変動します。時間が経つと、ネガティブなキーワードが再び表示されることがあります。例えば、新たな問題が発生したり、ネガティブな検索が増加したりすると、非表示になっていたキーワードが再出現する可能性があります。
そのため、サジェスト対策は「一度解決して完了」するものではなく、定期的な監視と更新が必要です。企業は継続的にサジェストをモニタリングし、必要に応じて対策を更新する「メンテナンス型」のアプローチを取ることも重要です。
まとめ
検索エンジン上の検索結果に悩む企業は決して少なくありません。問題を放置してしまうと、風評被害がさらに拡大し、企業に大きなリスクをもたらす可能性があります。
風評被害は、いつ企業に襲いかかってくるか分からないうえ、風評被害対策においては、「これだけやれば大丈夫」と言えるものでもありません。企業をリスクから守るためにも、様々な観点から包括的に対策を検討・実施していきましょう。
デジタルリスク対策は、エルテスへ