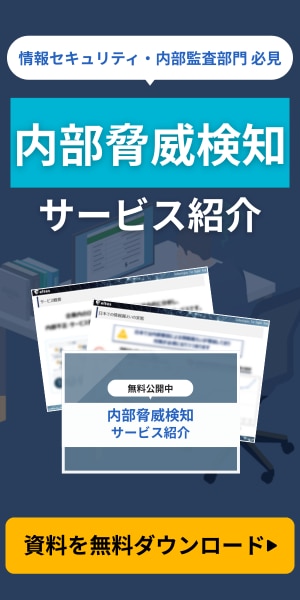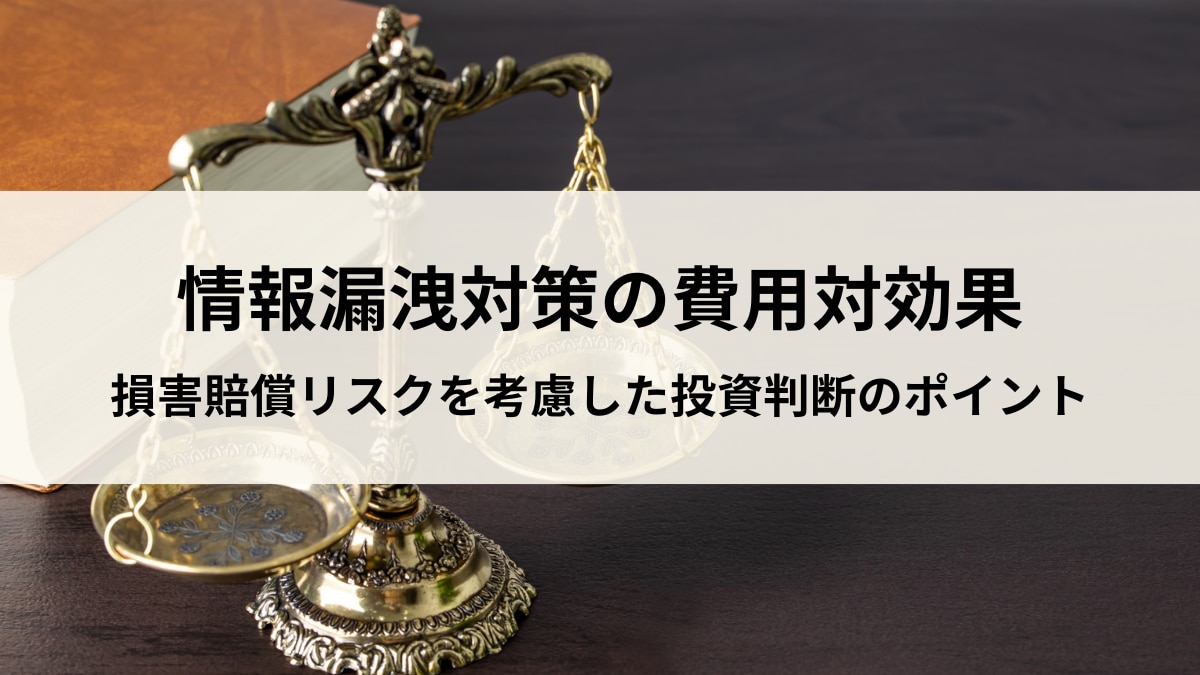
情報漏洩対策の費用対効果:損害賠償リスクを考慮した投資判断のポイント
情報漏洩対策の重要性は、現代のビジネス環境においてますます高まっています。情報漏洩が発生すると、企業の信頼性が低下し、顧客離れや損害賠償といった深刻な影響を引き起こす可能性があります。
とはいえ、限られたセキュリティ予算の中で、どこまで対策に投資すべきか判断に迷う担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、実際の損害賠償事例や法的リスクを踏まえつつ、DLPやログ監視、社員教育などの主要な対策の費用対効果をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
情報漏洩事例と影響
企業を襲う情報漏洩リスクは、深刻な経営リスクにつながります。ある大手美容系企業では、会員約5万人分の個人情報が流出、原告13名に対しては1人あたり3万5,000円、別の1名には2万2,000円の損害賠償を命じられました。
一方、ある大手IT企業の事件では約450万件の情報漏洩が発覚し、被害総額は100億円超と発表されました。判決では、約1,100万件分の漏洩に対し、被害者1人あたり6,000円の賠償が命じられました。
これらの事例からわかるように、漏洩件数が多いほど企業の対応負担は大きくなります。
漏洩した情報の項目がセンシティブなものを含まず一般的な連絡先情報にとどまり、二次被害もない場合は、慰謝料額は1人あたりおおむね「3000円~5000円」が相場と言われています。
一方、漏洩した項目がセンシティブな情報を含み、かつ、二次被害が出ているケースでは、1人あたり「35,000円」の損害賠償を認めた判例も存在します。
引用元:熊田法律事務所「情報漏洩発生時の損害賠償について解説」
しかし、実際の企業損失は賠償額をはるかに上回ります。情報漏洩による損害は、個人情報保護法違反による刑事罰や民事罰に加え、信用低下による新規受注減や取引停止、システム復旧コストの増大、問い合わせ対応による業務効率の低下など、間接被害が極めて深刻です。
以上のように、賠償リスクだけでなく、顧客信頼の喪失と企業評価への影響も考慮したリスク管理が求められます。
情報漏洩対策の投資項目
情報漏洩対策における投資項目は多岐にわたりますが、コストと効果のバランスを見極めることが重要です。
以下に代表的な対策を挙げ、費用感と効果を解説します。
DLP(Data Loss Prevention)
DLP(Data Loss Prevention)とは、企業や組織の機密情報が外部に漏れないよう、自動的に重要情報を特定し、送信や印刷などの操作を監視・制限する情報漏洩対策システムです。
例えば、従業員が会社の重要書類を持ち出す際に、セキュリティ担当者がチェックして不正な持ち出しを防ぐようなイメージであり、DLPはその仕組みをシステムで自動化することで、ミスや悪意による情報漏洩を未然に防ぎます。
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」報告書でも、情報漏洩のルートとして中途退職者による漏えい(36.3%)や、現職従業員の誤操作・誤認による漏えい(21.2%)など、内部要因が過半数を占めており、「人のミスや不正」を防ぐ仕組みとしてDLPは現在注目されています。
一方で、導入にはシステム構築費用、ライセンス費用、サーバー運用費用などが必要になり、初期投資が高額になりがちです。本当に費用に見合った機能が備わっているか、また目的から外れた機能が含まれていないかどうか、余分なコストの発生に注意が必要です。
ログ監視
システムのログには、利用状況やエラーメッセージ、不正アクセスの痕跡など、多くの重要な情報が記録されています。これらのログを適切に取得・分析することで、セキュリティの強化やトラブルの原因究明が可能となります。
前述の「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」報告書から、近年ではログ監視の重要性が高まっています。ログ監視とは、システムやアプリケーションが出力するログデータを常時確認し、不正アクセスや情報漏洩、システム障害といった異常を早期に発見するための仕組みです。また、内部不正や操作ミスの痕跡を把握することで、事故発生後の初動対応や原因追跡にも活用されます。
法令面でも、ログの適切な管理が求められています。2022年の個人情報保護法改正では、個人情報が漏洩した際の個人情報保護委員会への報告が義務化されました。漏洩の内容や原因、影響範囲を正確に把握・報告するためには、信頼性の高いログの取得と保管が不可欠です。
このような要請は業界ごとに発信されるガイドラインにも見られます。たとえば、金融庁が2024年10月に発表した「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」では、以下のように明記されています。
ログの取得・監視・保存のための手続を策定し、定期的にレビューすること。
これは単なる推奨事項ではなく、基本的な対応事項とされており、リスク評価や報告義務、さらには継続的なセキュリティ強化の前提として、ログ管理が欠かせない要素と位置づけられています。
一方で、ログ監視体制の整備には一定のコストが伴います。ログ監視ツールには安価なものから高機能な製品まで幅広い選択肢があり、システムの規模や目的に応じた選定が求められます。また、高度な分析を行うには専任担当者のスキルが必要であり、人材が不足している場合は外部の専門業者に委託するケースもあります。その分、運用コストが増加する可能性も考慮すべきです。
しかし、ログ監視を通じて異常を早期に発見できれば、情報漏洩などの重大なリスクを未然に防ぎ、対応コストを大幅に削減できます。信頼性の高いIT運用を実現するためにも、計画的かつ継続的なログ管理体制の構築が不可欠です。
コンプライアンス教育
技術対策と並んで、コンプライアンス教育も重要な対策です。メール誤送信やUSB紛失、権限設定ミスなど多くの漏洩は人的ミスに起因しています。
定期的な情報セキュリティ教育やフィッシング訓練により社員のセキュリティ意識を高めることで、漏洩事故の発生頻度を下げられます。教育は比較的低コストで導入できる一方、効果には限界もあり、繰り返しの教育や運用ルールの遵守チェックと組み合わせる必要があります。
セキュリティ対策に活用できるサービスの紹介
エルテスの「内部脅威検知サービス(Internal Risk Intelligence)」では、豊富なデジタルリスク対策の実績に加え、過去の不正事例から構築されたリスクシナリオと機械学習技術を組み合わせることで、不審な行動の予兆まで捉えることができるのが大きな特徴です。
検知後は専門のアナリストが内容を精査し、必要に応じた対応策をご提案します。専任の監視要員がいない企業でも、安心してご利用いただけます。
▶ Internal Risk Intelligenceサービスの詳細はこちら
セキュリティ教育に活用できるサービスの紹介
エルテスでは、毎月デジタルリスクに関するオンラインセミナーを開催しています。コンプライアンスにとどまらず、企業のリスク対策に役立つ情報やトレンドを発信しており、継続的な学びの機会としてご活用いただけます。
また、従業員起因のデジタルリスクについてマンガ形式で学べる教育教材も提供しており、多くの店舗や従業員を抱え、研修の実施が難しい企業にとっては、効果的なコンプライアンス教育手段となります。
▶【研修支援】リスコミ(SNSリスクのマンガ教育教材)の詳細はこちら
情報漏洩対策は、エルテスへ
まとめ
法改正やサイバーリスクの多様化により、情報セキュリティへの対応は、どの企業にとっても欠かせない課題となっています。ログ監視や内部脅威の検知、日常的なセキュリティ教育といった対策を組み合わせることで、リスクを早期に察知し、被害を防ぐことができます。
こうした対策は、自社だけで完結させる必要はありません。専門的な知見や外部サービスを上手に活用しながら、自社に合った無理のないセキュリティ体制を整えていきましょう。