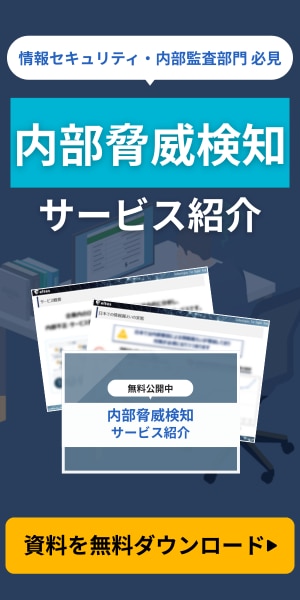情報漏洩のリスクは?発生する原因と有効な対策方法を解説
情報漏洩は、個人情報や機密情報を保有する企業にとって常に存在するリスクです。万が一情報漏洩が発生した場合は、金銭的な損失や処罰などのリスクに発展する可能性があります。情報漏洩を未然に防止するためには、原因の把握と対策が必要不可欠です。
担当者のなかには、「情報漏洩について学びたい」「情報漏洩に起因するリスクや対策について知りたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。この記事では、情報漏洩に起因するリスクや原因、未然に防止する方法を解説します。
目次[非表示]
情報漏洩に起因するリスク一覧
情報漏洩が発生した場合、金銭的損失や情報の悪用など、さまざまなリスクが想定されます。起こり得るリスクを把握しておくことで、情報漏洩の影響力をより深く理解することが期待できます。ここでは、情報漏洩に起因するリスクを5つ紹介します。

①損害賠償
情報漏洩が発覚した場合、被害者から損害賠償請求される可能性があります。情報漏洩の規模によって被害者の人数は膨大になるため、損害賠償額が高額になるケースも少なくありません。
②刑事罰
情報漏洩で法律違反が認められた場合、国から刑事罰や罰金が課せられる可能性があります。 企業だけではなく、従業員個人に課せられるケースもあります。
③社会的信用の損失
情報漏洩は、会社の社会的信用の損失につながります。近年ではSNSで悪い評判が広がりやすくなっていることもあり、結果として株価の下落につながることも予想されます。また、情報漏洩は顧客離れや、取引先との関係も解消される可能性があり、企業にとって悪影響を及ぼします。
④データの悪用
個人情報や機密情報が流出した場合、悪意のある第三者によって悪用される可能性があります。 個人情報は迷惑メールや詐欺、機密情報は競合他社に利用されるケースが想定されますが、いずれにせよ企業への悪影響に繋がる恐れがあります。
⑤なりすまし
IDやパスワード、クレジットカード情報などが流出した場合、第三者のなりすましに使用される可能性があります。企業になりすまして迷惑メールの拡散やアカウントの乗っ取り、クレジットカードの不正利用などの被害が想定されます。
情報漏洩が発生する原因
情報漏洩の原因は大きく分けて、サイバー攻撃・ヒューマンエラー・内部不正の3つに分類できます。サイバー攻撃による大規模な漏洩事件が目立ちますが、一方でヒューマンエラーや内部関係者による漏洩も依然多く発生しており、対策が重要です。
①サイバー攻撃
外部の第三者による不正アクセスやマルウェア感染など、サイバー攻撃は情報漏洩の主要因です。
近年では従来の無差別な「ばらまき型攻撃」よりも、特定の企業や組織を狙った「標的型攻撃」が増加しています。実際、東京商工リサーチ社が2025年1月に公表した調査データによればウイルス感染やハッキング等の外部攻撃が情報漏洩原因の約55%を占め、最大の割合となっています。
②ヒューマンエラー
従業員の人的ミスによって生じる情報漏洩も少なくありません。例えば、メールの宛先や設定ミスによる誤送信、機密ファイルの添付ミス、社用PC・USBメモリの紛失・置き忘れ、クラウド設定の誤りによる情報公開などが典型例です。
情報漏洩インシデント全体の約32%はヒューマンエラーによるものであり、メール誤送信が21.6%、紙資料の紛失・誤廃棄が10.5%と報告されています。
ヒューマンエラーを防ぐには、社員教育の徹底や送信前チェック体制の強化、端末やデータの暗号化など基本的対策が有効です。
③内部不正
企業内部の関係者が不正な目的で情報を持ち出す行為も、重大な情報漏洩の原因の一つです。一度起こると流出規模が甚大になる傾向があります。
内部不正の動機としては、金銭目的で名簿業者などに個人情報を売却するケースや、転職先に持ち込むためのデータ持ち出し、あるいは恨みによる暴露行為など、さまざまなものがあります。
こうした内部犯行は発覚しづらく、被害が拡大するリスクが高いため、アクセス権限の適切な管理、ログの監視体制、内部通報制度の整備など、多層的な対策が求められます。
情報漏洩の事例3選
以下に、日本国内で発生した代表的な情報漏洩事件を3件取り上げ、それぞれの漏洩原因・対応措置・社会的影響の観点から解説します。

事例①:業務委託先のUSBメモリ紛失による情報漏洩
ある自治体が委託していた業務委託先の社員によって、市民約46万人分の個人情報を保存したUSBメモリが一時的に紛失する事故が発生しました。
この社員は、業務のため、住民基本台帳などのデータを保存したUSBメモリを業務目的で持ち出していました。しかし、業務後にかばんごと紛失してしまいました。その後、警察による捜索によりUSBメモリは回収され、自治体は調査委員会を設置したうえで「個人情報の漏洩は確認されなかった」と発表しました。
調査報告では、USBメモリの持ち出しに関する事前許可の取り決めがあったにもかかわらず、委託社員がそのルールを認識しておらず、さらに委託元による教育・監督体制も不十分だった点が厳しく指摘されました。
これを受けて自治体は、USBメモリを含む外部媒体の持ち出しに関する手順やルールの周知徹底、委託先を含む情報管理体制全体の再構築に取り組む方針を打ち出しました。
事例②:標的型メールをきっかけとした公的機関での情報漏洩
ある公的機関において、職員が受信したメールの添付ファイルを開封したことでマルウェアに感染し、端末が乗っ取られるという事件が発生しました。その結果、内部システムが外部から不正アクセスを受け、大規模な情報漏洩に発展しました。
感染した端末が踏み台となり、基幹システムから氏名、識別番号、生年月日、住所などの個人情報が大量に引き出され、国民の不安を招く重大なセキュリティインシデントとなりました。
組織は、発覚後すぐに記者会見で事実を公表し謝罪を行いました。加えて、専用の相談窓口の設置や、対象となる可能性のある個人への郵送での説明および謝罪文の送付、さらには必要に応じた個人識別番号の再発行など、被害者対応を進めました。
事例③:教育機関でのヒューマンエラーによる個人情報の誤送信
ある大学では、職員が海外の提携先に送付する名簿ファイルを作成する過程で、全学生の情報が含まれたマスターデータのシートを削除し忘れるというミスが発生しました。その結果、メールでファイルを送信した際に、本来関係のない全在籍学生の個人情報が外部に誤って提供されてしまいました。
大学側は誤送信に気づくとすぐに送信先に連絡を取り、ファイルの削除を依頼・確認しました。また、対象となる学生への個別通知と謝罪を行い、再発防止策として全職員への注意喚起や、メール送信時の添付ファイル確認を徹底するルール強化に取り組んでいます。
今回の件は、幸いにも情報が悪用されたとの報告は出ていませんでしたが、「大学でもこのようなミスが起こるのか」としてネット上でも話題となりました。他の教育機関にも波及的な注意喚起がなされ、組織の規模を問わず、ヒューマンエラー防止の仕組み作りが求められることを改めて示す事例となりました。
情報漏洩を未然に防ぐ方法
情報漏洩は、適切な対策を講じることで未然に防げる場合があります。対策のなかにはコストがかかるものもあるため、予算不足の場合は社内ルールの見直しやアクセス権限の付与などの対策が有効です。
ここでは、リソース不足のなかでできる情報漏洩対策を紹介します。
①ルール・ガイドラインの策定
情報管理に関するルールやガイドラインを策定することで、社内全体で情報セキュリティに対する意識を共有できます。定期的に教育の機会を設けることで、セキュリティ意識を維持していくことが可能です。
②アクセス権限の付与
情報に対する適切なアクセス権限を従業員に付与することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。データだけではなく、サーバー室への入室制限を設けるなど物理的なアクセス制限も、より強固なセキュリティ体制に寄与できます。
③セキュリティシステム・ツールの導入
セキュリティシステムを導入することで、ウイルス感染や不正アクセスのリスクを軽減できます。また、サイバー攻撃の手口は日々変化するため、システムを常に最新の状態に保つことが大切です。
企業で起こるリスクに早く気づくために
エルテスでは、PCのアクセスログや印刷ログ、サイトの閲覧ログなど企業の様々なログデータを横断的に分析し、内部不正や情報持ち出しに至る行動の予兆を検知するサービス「Internal Risk Intelligence」を提供しています。
勤怠データやPCのアクセスログデータなどの複数のデータを活用し、従業員の情報持ち出しや内部不正が発生する予兆や可能性を検知します。
また、近年はSNSが絡んだ情報漏洩や流出した情報がネット上に公開、拡散されてしまうことも問題とされています。SNSやネット上を日々モニタリングすることも、被害の深刻化を防ぐ対応として有効です。
▼「Internal Risk Intelligence」 で検知できるリスクの詳細はこちら
▼SNSやネットのモニタリングによるリスク対策事例の詳細はこちら
まとめ
この記事では、情報漏洩について以下の内容で解説しました。
- 情報漏洩に起因するリスク一覧
- 情報漏洩が発生する原因
情報漏洩の事例3選
情報漏洩を未然に防ぐ方法
情報漏洩は些細なきっかけで発生する場合があるため、個人情報や機密情報を保有する企業は常に細心の注意を払う必要があります。情報漏洩が発覚した場合は、社会的信用の損失に加え、損害賠償や刑事罰に発展するケースも考えられます。
適切な対策を講じるためには、正しく原因や発生後のリスクを把握し、必要な対応をすることが大切です。
エルテスは、企業を守るためのデジタルリスクマネジメントを専門としたサービスを提供しています。社内の体制構築からリスクの検知、クライシス発生後のリスク対応、評判回復まで、一貫した支援が強みです。デジタルリスクにお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
情報漏洩対策は、エルテスへ