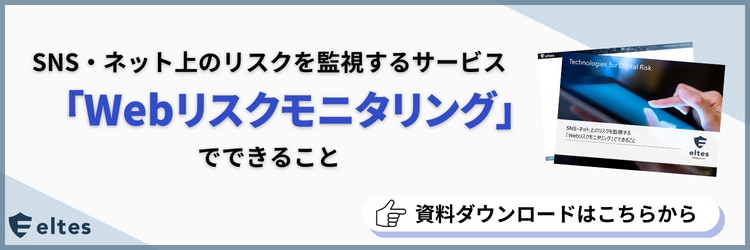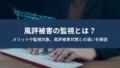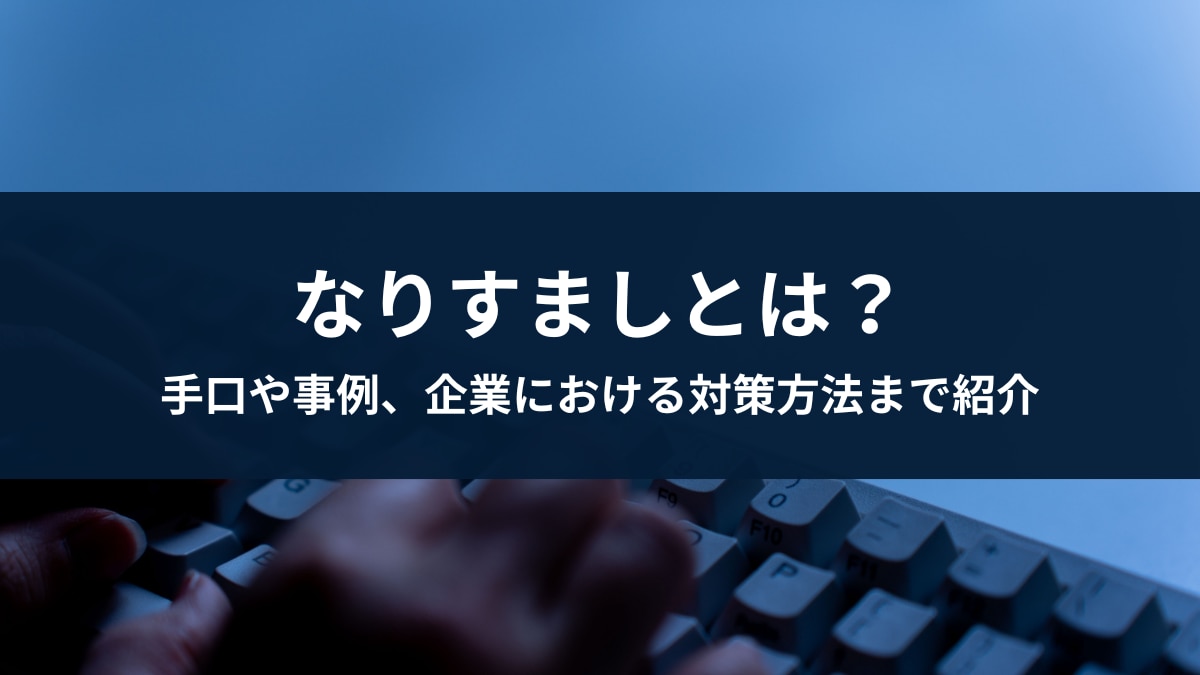
なりすましとは?手口や事例、企業における対策方法まで紹介
情報が瞬時に共有され、デジタル社会が進展する今、SNSやウェブサイトで他人や企業になりすます手口がますます増えています。
この記事では、なりすまし被害の具体的な事例を取り上げ、企業がどのような対策を取るべきかを分かりやすく解説します。
▶【お役立ち資料】SNS別なりすましアカウントの報告方法はこちら
目次[非表示]
- 1.なりすましとは?
- 2.なりすましの手口
- 2.1.SNSのアカウント偽造
- 2.2.ウェブサイトの偽造
- 2.3.フィッシング
- 3.企業におけるなりすましの実際の事件
- 3.1.SNSアカウント偽造の事例
- 3.2.ウェブサイト偽造の事例
- 3.3.フィッシングの事例
- 4.企業が行うべきなりすまし対策
- 4.1.アクティビティの監視(モニタリング)
- 4.2.情報管理のルールを固める
- 4.3.認証を強化する
- 4.4.社内のセキュリティ意識を高める
- 4.5.定期的に社内セキュリティの見直しを行う
- 5.デジタル時代のリスク対策ならエルテス
- 6.まとめ
なりすましとは?
なりすましとは、他人のふりをして、まるで本人であるかのように振る舞う行為を指します。例えば、X(旧Twitter)などのSNSでは、IDやパスワードを盗んでアカウントを乗っ取るケースや、他人の名前やプロフィールを使って偽のアカウントを作成するケースが見られます。技術の進化とともに、なりすましの被害は世界的に増加し、新たな手口が次々と生まれています。
▶【コラム】万が一X(旧Twitter)が乗っ取られたときの対処法はこちら
なりすましの手口
なりすましは、どのような手口で行われるのでしょうか。
ここでは代表的な方法として、SNSのアカウント偽造、ウェブサイトの偽造、そしてフィッシングについて紹介します。

SNSのアカウント偽造
「SNSのアカウントの偽造」とは、本人の投稿や画像を無断使用し、本人のように見せるアカウントを作成する手口です。特に影響力のある有名人や企業、政府機関のアカウントに対して行われやすいです。
偽造アカウントは、一般ユーザーが興味本位で作成することもありますが、多くは悪意を持つ人物によって運用されています。不適切な発言で本人の名誉を傷つけることや、詐欺目的で金銭や個人情報を狙う場合もあります。
ウェブサイトの偽造
ウェブサイトの偽造は、正規のサイトと見分けがつかないほど、よく似た偽サイトを作成し、情報を盗む手口です。本物のロゴやデザインを再現し、ユーザーに本物と思わせます。
偽サイトに誘導されたユーザーは、実在しない商品を購入しようとし、商品が届かないなどの金銭的損失や、商品購入時に登録した個人情報が不正に使用される被害などを受けることになります。
中には存在しない店舗や商品のサイトを装い、購入者から個人情報を引き出す手口もあります。
フィッシング
フィッシングは、「ウェブサイトの偽造」を活用した代表的ななりすまし手口で、特にネット犯罪で使われることが多いです。
銀行やクレジットカード会社など、信頼性の高い企業を装った通知を送り、「情報確認のため」などの理由でリンクをクリックさせ、偽サイトに誘導します。ユーザーは、その偽サイトが本物と見分けがつかないため、ログイン情報やクレジットカード番号を入力してしまい、入力された情報を盗み取られる手法です。
企業におけるなりすましの実際の事件
なりすましの手口を理解したうえで、実際にどのような事例が発生しているのかを見ていきましょう。
SNSアカウント偽造の事例
ある自治体が実施したSNSキャンペーンにおいて、公式アカウントを装った偽アカウントによるなりすまし被害が発生した事例です。
このキャンペーンは応募した中から抽選でプレゼントが当たるというもので、開始から多数の応募が集まりました。しかし、偽アカウントから応募者に、偽の当選通知のDMを送られてしまい、個人情報や金銭が詐取される手口が確認されました。
被害を受けた自治体は応募締切を予定より早める対応を余儀なくされました。このような事態は、公式運営への信頼低下や今後のキャンペーンへの影響が懸念されます。
ウェブサイト偽造の事例
公式ブランドを装った偽通販サイトによるなりすまし被害が発生した事例です。
SNS広告経由で偽サイトへ誘導し、購入したユーザーには注文とは異なる偽物や模倣品を送付する手口が複数確認されています。
このような事態は、ブランドイメージの低下や顧客対応の負担増加を引き起こします。さらに、正規商品の売上減少や長期的な収益への悪影響も懸念されます。
フィッシングの事例
金融機関になりすまし、SMSやメールを使ったフィッシング被害が発生した事例です。
ユーザーには「お客様の口座の取引を一時的に規制しています」などの偽メッセージが送られ、リンクをクリックするとネットバンキングを装った偽サイトに誘導される仕組みが使われています
偽サイトでは、契約者番号や口座番号、パスワードなどを入力させ、個人情報を不正に収集する手口が確認されています。
組織的な不正の可能性も高く、新たな手口による被害拡大も懸念されています。このような事態は、金融機関以外でも考えられ、ユーザーからの信頼を損なうリスクを引き起こします。セキュリティ対策が不十分と見なされた場合、ユーザーが利用を控えたり、他の金融機関への切替を検討する可能性も高まります。
企業が行うべきなりすまし対策
企業が行うべきなりすまし対策として、いくつかの重要なポイントがあります。

アクティビティの監視(モニタリング)
なりすましによる被害を防ぐためには、企業が自社のシステムやネットワーク上で発生するあらゆるアクティビティを継続的に監視し、怪しいトラフィックや異常な行動を早期に検出することが重要です。モニタリングのシステムやツールを導入し、異常な行動パターンや信頼性の低いアクセスを検知する仕組みを整えることが効果的です。
また、企業内部だけではなく、SNSなどネット上の投稿など外部情報もモニタリングできるとさらに効果的です。特に偽のSNSアカウントやWebサイトなどを早期に見つけられる体制を整えておくことも推奨します。
監視体制を構築することで、企業は自社の資産や顧客情報を保護し、信頼性を維持することができます。また被害を最小限に抑え、なりすまし行為による金銭的損失や法的リスクからも企業を守ることができます。
情報管理のルールを固める
企業が情報管理を徹底するためには、明確なルールを策定し、それを確実に実施することが重要です。
例えば、機密情報へのアクセス権限は必要最低限の従業員に限定し、各権限に応じたアクセス制御を行うことで、内部不正や外部からの侵入を防止できます。アクセス権限は一度設定して終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて更新する必要があります。
適切なアクセス管理が行われないと、情報セキュリティの弱点となり、乗っ取りやサイトの改ざんリスクを高める原因となってしまいます。
認証を強化する
SNSのなりすまし対策には、アカウント認証の強化も欠かせません。
まず、複雑なパスワードの設定は基本ですが、意外と見過ごされがちです。数字や記号を組み合わせたパスワードを使用し、定期的に変更しましょう。また、サイトごとに異なるパスワードを設定することも、一つの情報漏洩が他のアカウントに及ぼす影響を防げます。
さらに、多要素認証(MFA)を導入することも効果的です。MFAを使えば、パスワードが盗まれても追加の確認が必要になるため、不正アクセスを防げます。
社内のセキュリティ意識を高める
社内のセキュリティ意識の向上は、組織の安全を守るために欠かせません。
フィッシングの被害に従業員が遭うのも考えられるため、「自分も標的になり得る」という意識と知識を習得してもらうことで、セキュリティリスクの未然防止が可能です。
メールやSNSは特に攻撃対象となりやすいため、偽の送信元を見極めるスキルを向上させるために定期的な研修や教育が必要です。
定期的に社内セキュリティの見直しを行う
システムやネットワークのセキュリティ監査や脆弱性評価を定期的に行い、潜在的なリスクを把握することで、適切な対策を講じることができます。
特に、IDやパスワードを盗んで乗っ取ろうとするなりすまし攻撃や情報漏洩を防ぐためには、早期発見と迅速な対応が重要となります。
▶【お役立ち資料】SNS別なりすましアカウントの削除依頼方法はこちら
デジタル時代のリスク対策ならエルテス
なりすまし対策として、株式会社エルテスではお客様に以下の3点を中心とした包括的なサポートを提供しています。
- SNSのなりすましアカウントの調査とリスクの可視化
- SNSのなりすましアカウントの早期発見と対応支援
- なりすましアカウントが発生したときの社内エスカレーションフローの構築
SNS上で発生するなりすましアカウントの早期検知や、被害を最小化したいとお考えの方に最適です。
まとめ
なりすましは、個人や企業にとって深刻なリスクです。しかし、日常的な対策を徹底することで、被害を未然に防ぐことができます。
SNSやウェブサイトの監視、情報管理の強化、セキュリティ意識の向上を行い、必要に応じて専門家の力を借りてリスクを最小限に抑えましょう。