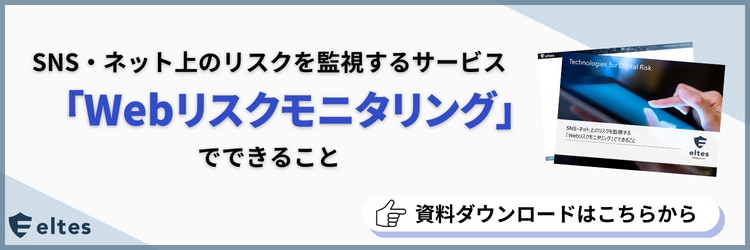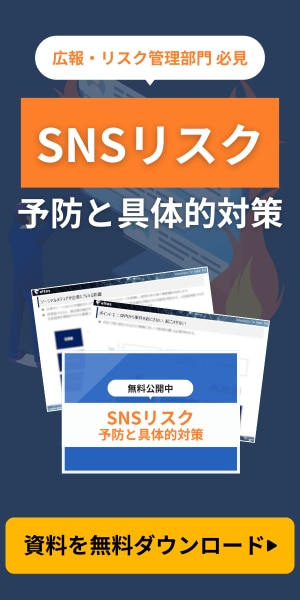X(旧 Twitter)の投稿監視とは?投稿を監視する理由や監視サービスについて解説
X(旧Twitter)は、拡散力の高さや投稿のしやすさなどから、情報発信の場として多くの企業や個人に利用されています。しかし、その一方で不適切な投稿やネガティブな口コミが炎上につながるリスクも抱えています。こうしたリスクを防ぐために重要なのが投稿監視です。
目次[非表示]
- 1. そもそも投稿監視とは?
- 2.SNS投稿監視サービスとは?
- 3.SNS投稿監視サービスの活用メリット
- 4.企業がX(旧 Twitter)の投稿を監視すべき理由とは?
- 4.1.拡散力が高いメディアである
- 4.2.炎上の早期発見や早期対応に有効
- 4.3.従業員の炎上の予防に有効
- 5.X(旧 Twitter)監視を行わないリスクは?炎上事例を紹介
- 6.X(旧 Twitter)監視するにはどのような方法がある?
- 6.1.X(旧Twitter)で監視
- 6.2.Yahoo!リアルタイム検索で監視
- 6.3.Googleアラートで監視
- 6.4.X(旧Twitter)監視サービスの利用
- 6.5.X(旧Twitter)管理・分析ツールの活用
- 7.投稿監視サービスの種類
- 8.X(旧 Twitter)の投稿を監視できる投稿監視サービスの比較ポイント
- 8.1.1.投稿の収集範囲
- 8.2.2.検知のスピード
- 8.3.3.危機発生時のサポートの有無
- 8.4.4.AIによるリスク判定機能の有無
- 9.エルテスのWebリスクモニタリングサービス
- 10.まとめ
そもそも投稿監視とは?
投稿監視とは、SNSや掲示板、ブログといった様々なネット上のメディアから、企業や商品・サービスなどに関する情報を収集して、炎上などのリスクとなる投稿がないか監視することを言います。
リスクとなる投稿の例として、飲食店における食品への異物混入や店員の対応の不備、CMなどプロモーションに対する批判、社内情報の流出などが挙げられます。
SNS投稿監視サービスとは?
SNS投稿監視サービスとは、自社やサービスに関連するWeb上の投稿や情報を監視・リスクを早期検知し、緊急通知や沈静化までの初期対応を支援するサービスです。
近年、マスメディアを介しての情報発信だけでなく、ユーザー自身がSNSに不満を書き込み、拡散され炎上が起きることも増えています。事件や事故に至らずとも、こうした不満が蓄積することで、サービスやプロモーションが停止に追い込まれるケースもあります。
SNS投稿監視サービスを導入することで、リスクを早期に察知し、適切な対応が可能です。
SNS投稿監視サービスの活用メリット
SNS投稿監視サービスを導入することで、SNS上での風評や炎上リスクをいち早く察知し、初動対応を迅速かつ的確に進めることができます。特に、夜間や週末など監視が手薄になりがちな時間帯でも、24時間365日体制で投稿を監視することで、気づいたときには炎上していたという最悪の事態を未然に防ぐことができます。
また、トラブルが発生した際には、専門家のサポートを受けながら初動対応を進められるため、謝罪文や声明の作成も安心して行えます。監視業務を専門サービスにアウトソーシングすることで、社内リソースの負担を減らし、従業員は本来の業務に専念することができます。
さらに、投稿内容を分析することで、サービス改善やマーケティング施策の立案に役立てることも可能です。
企業がX(旧 Twitter)の投稿を監視すべき理由とは?
企業が投稿監視を行う上で、大きな鍵となるメディアがX(旧Twitter)です。しかし、なぜX(旧 Twitter)の投稿を監視すべきなのでしょうか。それには大きく以下の3つの理由があります。
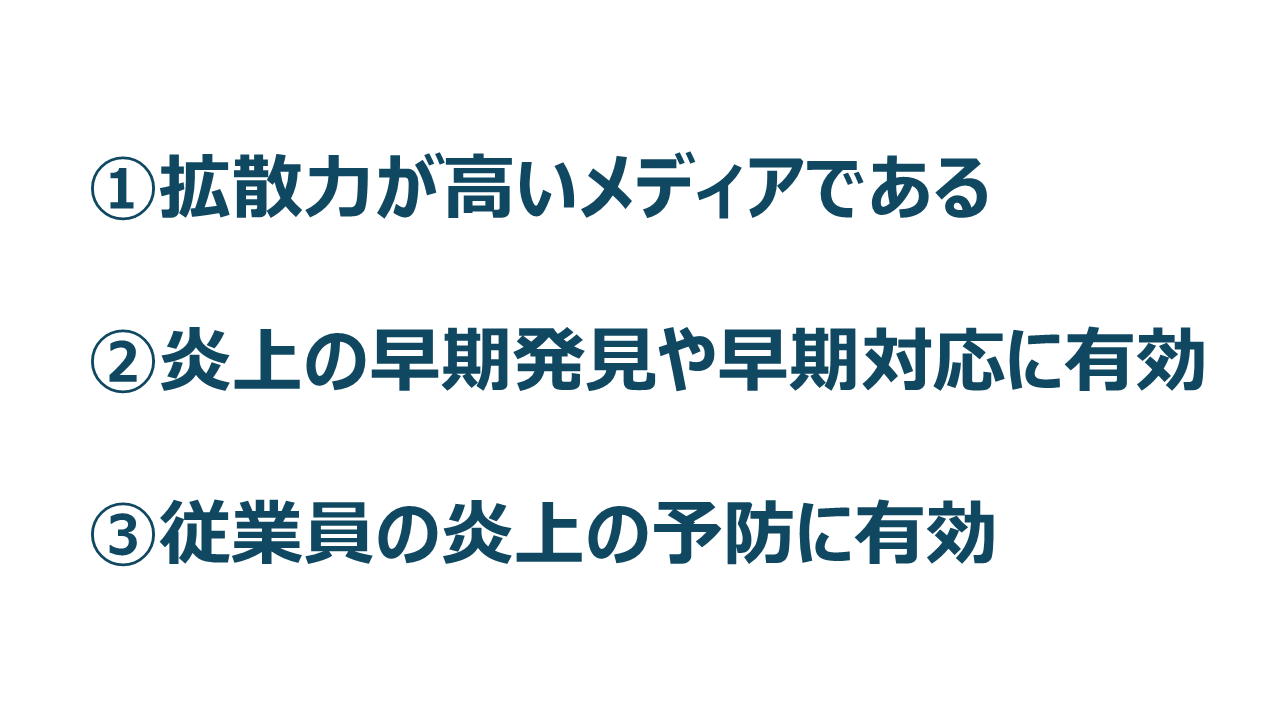
拡散力が高いメディアである
X(旧Twitter)の大きな特徴の一つとして、拡散力が非常に高いことが挙げられます。
リポスト機能やタイムラインの仕組みによって、自分がフォローしていないアカウントの投稿も簡単に閲覧することができます。そのため、あらゆる投稿を見る機会が多く、話題が一気に広がる傾向があります。
炎上リスクがある投稿に一度注目が集まると、瞬く間に拡散され炎上していく可能性があります。
炎上の早期発見や早期対応に有効
SNSの炎上は発生を予測することが難しく、発生した場合は非常に早いスピードで広まっていきます。万が一、発見と対応に遅れが生じると、被害が拡大する可能性があります。そのため、炎上の火種となる投稿をいち早く発見することが非常に重要です。
X(旧Twitter)は、多くのユーザーが日夜問わず、多岐にわたる投稿を行っています。企業のイメージ損失のリスクを抑えるためには、話題が集まりやすいX(旧Twitter)を監視することが求められます。
従業員の炎上の予防に有効
X(旧Twitter)では、従業員のプライベートで使用しているアカウントが炎上する可能性もあります。
プライベートな内容でも不適切な投稿で炎上した場合、所属企業を特定される事態にもなりかねません。フォロワーしか見られない鍵付きのアカウントや親しい人達だけへの限定公開にしていた場合でも、情報が流出し炎上に繋がったケースも過去にはありました。
SNSが社会に浸透した今、従業員のSNS利用を禁止することは現実的に難しいため、日常的に自社に関する情報を監視して炎上リスクを早期に発見することが大切です。また、社内でSNSの利用方法のガイドラインを制定したり、ルールを浸透させる研修を実施することで、さらに炎上予防の効果が期待できます。
X(旧 Twitter)監視を行わないリスクは?炎上事例を紹介
X(旧Twitter)を多くの企業が利用するようになり、炎上の発生も業界問わず頻繁に見られるようになりました。
実際にX(旧Twitter)上で発生した炎上事例について紹介します。
テーマパークの公式アカウントの炎上
第二次世界大戦で長崎市が原子爆弾を投下された日に、テーマパークの公式X(旧Twitter)アカウントの投稿が炎上しました。
投稿内容は、あるアニメーション作品から引用した「なんでもない日におめでとう」というメッセージであり、投稿日を考慮するとふさわしくない内容であると批判が殺到しました。
その後、テーマパークの公式アカウントは該当の投稿を削除し、謝罪文を公開しました。
食品メーカーのキャンペーンによる炎上
ある食品メーカーが、X(旧Twitter)で抽選のプレゼントキャンペーンを実施しました。しかし、ユーザーから「当選しているのはフォロワー数の多いアカウントばかりである」といった指摘があり、それが拡散され炎上しました。
その食品メーカーは投稿を停止し静観の対応をとっていましたが、結果的に事態に関する調査を実施し、X(旧Twitter)上で謝罪と再抽選をする結果に至りました。
X(旧 Twitter)監視するにはどのような方法がある?
企業がX(旧Twitter)を監視する方法には、無料ツールや外部サービスなど様々な選択肢があります。ここでは5つの方法を紹介します。自社の状況や方向性にあった方法で監視をしましょう。

X(旧Twitter)で監視
まずは、X(旧Twitter)の検索機能を使用する方法です。社名やサービス名を検索して目視で監視します。
X(旧Twitter)の検索機能には、条件を付け効率的に検索ができる「検索コマンド」や「高度な検索」といった機能があります。「高度な検索」を使うと、一定数以上の返信やリポストの投稿に絞ることも可能なため、拡散されている批判投稿を察知することに活用できます。
しかし、手動で見ることになるため監視できる投稿に限界があるなど、注意が必要です。
Yahoo!リアルタイム検索で監視
Yahoo! JAPAN が提供するYahoo!リアルタイム検索を利用する方法もあります。検索窓にキーワードを入力して検索すると、そのキーワードが含まれるリアルタイムの投稿が確認できます。
また、そのキーワードを含む投稿件数の推移や、ポジティブもしくはネガティブといった感情の割合も見ることができます。これらのデータは、炎上の発見はもちろん、ユーザーの論調の把握に役立てることも可能です。
しかしYahoo!リアルタイム検索は、投稿を遡れる期間が過去30日までという制限があります。
Googleアラートで監視
Googleアラートとは、登録したキーワードを含む情報がWeb上に流れた際に通知されるGoogleのサービスです。X(旧Twitter)以外のメディアの情報なども確認できます。
キーワードの設定の他に、通知の頻度や時間、ブログやニュース情報の取得の有無といったカスタマイズが可能です。
ただし、詳細な条件設定はできないうえ、不要な内容まで届くことがあるため、取得した情報の精査が必要になります。取得する精度も正確ではないため、他のツールとあわせて使うことを推奨します。
X(旧Twitter)監視サービスの利用
X(旧Twitter)の投稿監視を行ってくれるサービスを利用すれば、24時間365日の監視が可能になります。
サービスによって、AIによるリスク検知や、専門家による精度の高い監視など様々な特徴があります。また、炎上した際の対応をサポートしてくれるサービスもあるので、自社の方針や監視目的に合わせてサービスを選びましょう。
X(旧Twitter)管理・分析ツールの活用
X(旧Twitter)の管理・分析ツールは炎上対策の他に、効率的な運用のサポート機能が搭載されています。具体的には、アカウントの管理や投稿予約、インプレッション数などの投稿分析といったものがあります。
設定したキーワードで投稿を収集してくれる機能も多いため、社名やサービス名、リスクとなり得るキーワードを事前に登録すると炎上対策として活用できます。
投稿監視サービスの種類
投稿監視サービスの種類は、大きく「目視タイプ」と「ツールタイプ」の2つがあります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを踏まえて、自社の体制・運用にあったタイプを選びましょう。
目視タイプ
1つ目は、人の目で監視する目視タイプです。ツールタイプと大きく異なる点は、その名の通り目視で監視を行う点です。リスクとなる投稿や指定の条件に合致した投稿が発見された場合は、電話やメールで通知してくれるものが多くあります。
目視タイプのメリットは、検知の精度が高いことです。人が直接投稿を確認し判断するため、リスクを見逃す可能性は低くなります。また多くのサービスで、相談窓口となる担当者が付くため、運用や炎上時の対応に関するサポートを受けることができます。このようなサポート内容はサービスによって異なるため、自社に合ったものを比較検討するとよいでしょう。
一方デメリットは、目視であるために人的コストがかかり、費用が高くなる点です。費用を抑えたい場合は、次で紹介するツールタイプが適しています。
ツールタイプ
2つ目は、リスク投稿を自動で検知するツールタイプです。キーワードを設定して、そのキーワードと合致した投稿があれば自動的に収集・通知される特徴があります。また、一定期間の投稿内容レポートをメールやWeb上で確認できるツールが多いです。
ツールタイプのメリットは、リソースを割かずにコストを抑えることができる点です。また、リスク検知以外にも、サービスの口コミやプレスリリースの反響の確認など、他部門での応用が可能です。
一方デメリットは、リスク投稿を検出する際、誤検知の可能性があることです。設定したリスクキーワードと異なる新たなリスクが発生した場合、都度設定する必要もあります。そのため、検知精度を優先させたい場合やリソースが割けない場合は目視タイプが適しています。
X(旧 Twitter)の投稿を監視できる投稿監視サービスの比較ポイント
前述した通り、投稿監視サービスによって様々な特徴があるため、自社に適したものがどれかしっかり比較検討する必要があります。ここでは、X(旧Twitter)の投稿監視サービスを選ぶ際のポイントを4つ紹介します。

1.投稿の収集範囲
1つ目は、X(旧Twitter)以外に、Instagram・FacebookなどのSNS、ブログ、匿名掲示板など、各種メディアをどこまでカバーできるかという点です。
拡散力の高いX(旧Twitter)など、炎上リスクが高くなるメディアを最低限抑えておくという方針の場合は、網羅性を求める必要はありません。
しかし他のメディアも監視することで、さらにリスク検知の精度が高くなります。
2.検知のスピード
目視の監視において、スタッフが毎分毎秒すべての投稿をチェックするのは現実的ではないため、一定の時間間隔で監視されします。
数時間ごとの監視を基準にしつつ、自社の業務形態やリスク管理に適した監視体制をとれるサービスを選択しましょう。
3.危機発生時のサポートの有無
リスクのある投稿が検知された際のサポート体制も、比較ポイントの1つです。
火種となる投稿はすべてが炎上に発展するわけではなく、そのまま収束していくケースもあります。企業は投稿を検知したときのリスクレベルの見極めや、クレーム発生が予想される場合の対応、さらには謝罪文の掲載の要否など、様々な判断を冷静かつ的確に行っていく必要があります。
こうした判断に不安がある場合は、サポート体制のあるサービスを選ぶことをおすすめします。
4.AIによるリスク判定機能の有無
目視の投稿監視サービスは、人が監視することによって検知精度に安心感を持てる一方、投稿量が多いと費用が高くなる傾向があります。この課題を解決する方法として挙げられるのが、AIで自動的に投稿リスクの判定ができるサービスです。
全ての投稿監視を人の作業で行う必要がなくなるため、より多くの投稿量に対応できるようになります。
しかし、投稿によっては言葉のニュアンスの解釈が難しい場合があり、AIのみでは誤判定も発生する可能性があります。現状の段階では、人とAIを組み合わせた監視体制を前提として活用を検討するといいでしょう。
エルテスのWebリスクモニタリングサービス
エルテスの「Webリスクモニタリングサービス」は、AIと人の目によって24時間365日、X(旧Twitter)を始めとした様々なメディアの投稿を監視できるサービスです。緊急性の高い投稿をいち早く検知でき、炎上の予防や早期対応に貢献します。また、専門性のあるコンサルタントが担当につき、リスク投稿検知時の対応などをサポートします。社内の負担を抑えた投稿監視・炎上対策に活用いただけます。
まとめ
X(旧 Twitter)は社会的にも特に浸透したSNSである一方で、拡散力が高くリスク対策の観点では炎上が発生しやすいSNSでもあります。X(旧 Twitter)を監視することは自社や従業員をリスクから守ることに繋がります。
外部に投稿監視を依頼する際は、ツールやサービスの違いやサポートの有無など自社の目的にあわせて機能を比較することを推奨します。まだX(旧 Twitter)の投稿監視を取り組んでいない企業は、予算や運用体制にあわせてリスク対策のひとつの手段としてぜひご検討ください。