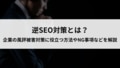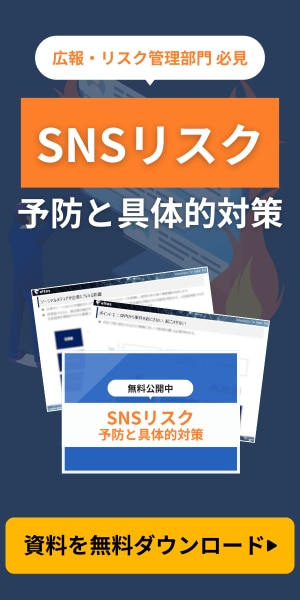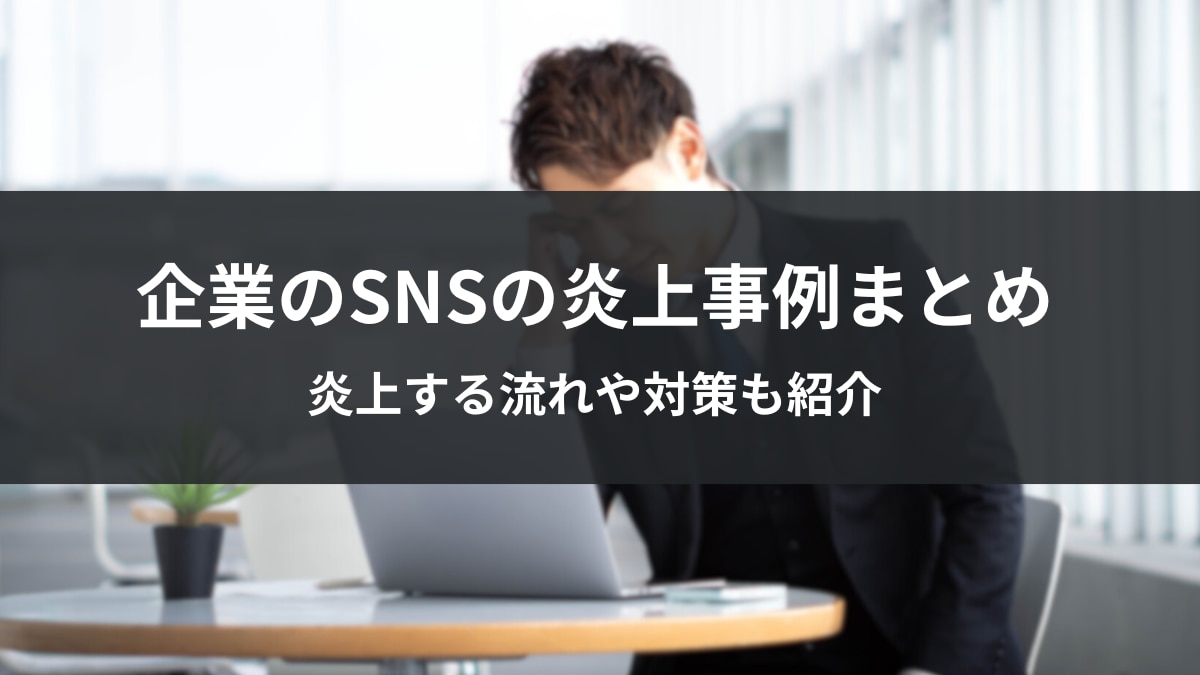
企業のSNSの炎上事例まとめ 炎上する流れや対策も紹介
近年、企業が商品やサービスの認知を広げ、ブランディングを強化するための方法としてSNSを活用することが一般的になっています。SNSには多くのメリットがある一方で、「炎上」のリスクも無視できません。炎上が発生する原因はさまざまであり、対策を講じるには事前に過去の炎上事例を把握しておくことが重要です。
この記事では、企業のSNSにおける炎上事例を紹介するとともに、炎上がどのように広がるのか、その流れや対策について解説します。
目次[非表示]
- 1.企業で起こったSNSの炎上事例
- 1.1.飲食店での迷惑行為による炎上事例
- 1.2.スポーツジムでの炎上事例
- 1.3.デリバリーチェーンでの炎上事例
- 1.4.サプリメント企業での炎上事例
- 1.5.ホテルの従業員による炎上事例
- 1.6.テーマパークでの炎上事例
- 1.7.人事担当者による炎上事例
- 1.8.プロモーション動画の炎上事例
- 1.9.人気アニメのグッズでの炎上事例
- 1.10.アパレルメーカーでの炎上事例
- 2.企業のSNSが炎上する原因
- 3.企業がSNSで炎上するまでの経過
- 4.企業のSNSが炎上している際の対処方法
- 4.1.迅速な原因究明
- 4.2.関係各所との情報共有
- 4.3.真摯な対応
- 5.炎上を未然に防ぐための対策
- 5.1.社内での教育・研修
- 5.2.運用マニュアル・ガイドラインの策定
- 5.3.炎上事例の継続的な収集・分析
- 5.4.ソーシャルリスニングサービスの導入
- 6.デジタルリスクに備えるならエルテス
- 7.まとめ
▼炎上が沈静化した企業の対応とは?SNS炎上の企業の対応事例はこちら
企業で起こったSNSの炎上事例
SNSの炎上というと、著名人の発言が話題になりやすいですが、企業においても広告の文言やキャンペーン内容など、些細なことがきっかけで炎上に発展するケースが多く見られます。
なぜ炎上が起こるのか、その原因やユーザーの反応を分析することで、今後の炎上対策に役立てることができます。ここでは、企業が直面したSNSの炎上事例を紹介します。
飲食店での迷惑行為による炎上事例
回転寿司チェーン店で、来店客が湯飲みや醤油ボトルの口を舐めたり、レーンの寿司に唾液をつけたりする様子を撮影した動画がSNSで拡散され、大きな炎上につながった事例です。
店側の過失ではありませんが、話題は大きく広がり、親会社の株価が急落する事態に発展しました。これを受け、店側は迷惑行為を行った男性に対し、損害賠償を求める訴訟を提起しています。
▼飲食店におけるリスクは他にも?飲食・食品製造業のデジタルリスクはこちら
スポーツジムでの炎上事例
セルフスポーツジムが、一部の会員にギフト券を謝礼として提供し、店舗の内装工事の「お手伝い」を募集したことで炎上した事例です。
報酬は最大7,000円分のギフト券でしたが、電気工事など資格が必要な作業や、専門道具の持ち出しを含む内容だったため、専門職に対する報酬の低さや、「お手伝い」という表現が不適切であると批判を集めました。
企業は会員にお詫びと訂正メールを送り、SNSでも釈明を行いました。「専門的な内容で、長時間お手伝いしていただく」という誤解を招いたことを認めつつ、本来は「お手すきの時間を活用して、簡単なお手伝いをしていただきたい」という主旨だったと説明しています。
デリバリーチェーンでの炎上事例
スタッフが店内で問題行動を行い、その様子を撮影した動画がSNSに投稿されて炎上する「バイトテロ」が社会問題となっています。
ある店舗では、スタッフが厨房でシェイクをヘラで舐め、周囲がはやしたてる様子をSNSに投稿したことで、批判が殺到しました。投稿したアカウントは削除されたものの、まとめサイトで取り上げられたことで、炎上が続きました。企業は謝罪しましたが、動画は転載され、ネット上に残ったままとなっています。
このような事態を防ぐには、店舗スタッフへの徹底したコンプライアンス教育が重要です。SNSに関するリスク研修を実施し、企業だけでなく従業員本人の人生にも影響を及ぼすことを理解させる必要があります。
また、勤務中の撮影禁止や、社内のSNS利用に関するルールの徹底も有効な対策です。企業はSNSを常時モニタリングし、問題行動を早期発見できる体制を整えましょう。
サプリメント企業での炎上事例
SNSを使ったPRの過程で、薬機法や景品表示法違反が起きて炎上する問題も度々発生しています。
あるサプリメント企業は、インフルエンサーを起用してPRを実施しました。しかし、「乾燥知らずのうるおい肌」などの表現が薬機法に抵触し、炎上しました。薬機法は、コスメやサプリメントなどの健康・美容関連商品も対象となります。
さらに、炎上初期の対応にも問題がありました。公式発表前に関係者が個人的な意見を発信し、説明なしに投稿を削除したことで、炎上をより拡大させる結果となりました。
こうした事態を防ぐには、関係者全員のコンプライアンス意識を強化し、法務のチェックを徹底することが不可欠です。特にインフルエンサーのように社外の人が関わる場合、表現のガイドラインや炎上時の対応マニュアルを策定しておくとよいでしょう。
また、炎上時は決して慌てず、感情的な対応を避け、冷静に対処することが重要です。
ホテルの従業員による炎上事例
ホテル従業員が、自身の勤務するホテルに有名人が宿泊していることをX(旧Twitter)に投稿し、炎上しました。投稿には俳優の名前や宿泊フロアなどの情報が含まれており、守秘義務違反として批判が殺到しました。従業員はアカウントを削除しましたが、個人情報が特定され拡散する事態となりました。また、ホテル側も「管理体制が甘い」と非難されました。
これを受け、ホテルは公式に謝罪し、従業員を厳正に処分すること、再発防止策として情報管理教育を徹底することを発表しました。
炎上後の真摯な対応はもちろん、日頃からこうした事例を防止できるよう徹底した従業員への教育が重要です。
テーマパークでの炎上事例
某テーマパークで、年間パスポートを持つ大人が子ども用のチケットで入場したとして、差額の支払いを求められる問題が発生し、SNSで議論が広がりました。
当事者の家族は、事実確認を待つ間は噓をついているように扱われたと主張しました。最終的にはテーマパーク側の誤解だったものの、対応に不満が残ったまま事態が進行し、炎上につながりました。その後、社長が当事者に謝罪のDMを送ったものの、その内容を自身のSNSアカウントで公開したことで、さらなる批判を招きました。
テーマパーク側には対応しようとする姿勢が見られましたが、慎重な判断が欠けていたために、結果として炎上を煽る形となってしまいました。
炎上は、発生後の対応が極めて重要です。SNS上のやり取りを含め、企業の危機管理としてあらかじめ方針を定め、一貫した対応を徹底しましょう。
人事担当者による炎上事例
企業の人事担当者が、個人のSNSに投稿した内容が拡散され、炎上した事例です。
投稿の内容は、「給料の金額や待遇で会社を選ぶ人とは働きたくない」という趣旨のものでした。これが議論を呼び、「給料にこだわることの何が悪いのか」「ブラック企業を彷彿とさせる」といった否定的な意見が相次ぎ、結果として企業イメージにも悪影響を及ぼしました。
近年、SNSは採用活動のツールとしても活用されるようになっています。個人的な意見の発信が企業の評判に影響を与える可能性があるため、慎重な対応が求められます。
対策として、SNSの使用に関する研修を実施し、発信内容に一定のルールを設けることが重要です。また、人事担当者がSNSを利用する場合は、発信の目的を明確にし、適切な運用を心がけましょう。
▼投稿前に使いたい!公式SNS投稿の炎上リスクチェックリストはこちら
プロモーション動画の炎上事例
プロのカメラマンが、新商品のプロモーションとして路上で一般人を撮影した「ストリートスナップ」が炎上しました。
このプロモーションは、不特定多数の人を撮影し、自社サイトで紹介するというものでした。しかし、撮影時に通行人の邪魔になる行為があった上、撮影された人の中には不快な表情を浮かべるシーンも見られました。モラルに欠けるとして批判が殺到し、企業はすぐに動画を削除しましたが、その後もSNSで転載され、炎上が続きました。
肖像権の取り扱いには慎重な対応が求められます。法的に問題がなかったとしても、ユーザーの批判を受けて炎上するとプロモーションの成果は出づらくなります。関連部署で十分に確認を行い、社会的なモラルやマナーに照らして問題がないかを検討しましょう。加えて、プライバシーがより重視される時代であることを再認識することが重要です。
人気アニメのグッズでの炎上事例
人気アニメの公式グッズとして販売された商品が、人種迫害の歴史に関連する腕章を連想させるデザインだったことから、国内外で批判を浴びました。
この腕章は原作にも登場し、物語の中では差別や迫害を丁寧に描いていたことから受け入れられていました。しかし、公式グッズとしてカジュアルに着用できる形で販売することは不適切だと指摘されました。原作ファンやアニメファンからも非難の声が上がり、最終的に公式は謝罪文を掲載し、販売を中止しました。
グッズ化を検討する際は、作品の背景を十分に理解することが重要です。世界には民族的・歴史的に許容されないものもあり、これまで問題がなかったものでも、時代の変化とともにタブー視されるケースがあります。歴史的背景を考慮し、多角的な視点でチェックを行う体制を整えましょう。
アパレルメーカーでの炎上事例
アパレルメーカーの広告キャンペーンが、パレスチナ・ガザ地区の侵攻を連想させるとして炎上しました。
このキャンペーンでは、海外モデルを起用し、壊れた壁や手足のない彫刻が雑然と散らばる白い部屋で、ジャケットを主役としたコーディネートを披露するという構図が採用されました。しかし、これがガザの街の爆撃後の様子を想起させるとして批判が殺到しました。SNSではボイコットを呼びかける声が広がり、X(旧Twitter)では関連するハッシュタグがトレンド入りする事態となりました。
その後、アパレルメーカーは広告を削除しましたが、親会社は「コンテンツの削除は通常の更新業務の一環であり、炎上とは無関係」と説明しました。また、キャンペーンの企画は7月に立案、9月に撮影されたものであり、イスラエルとハマスの紛争とは関係がないと強調しつつ、一部のユーザーに不快感を与えたことを謝罪しました。
広告の企画段階でのリスク管理が不十分だったことが問題視されました。国際情勢を踏まえ、誤解を招かないか慎重に検討し、文化的・政治的な影響を考慮することが必要です。
企業のSNSが炎上する原因
企業のSNSが炎上する原因としては次のようなものが例として挙げられます。
- ユーザーを不快にさせる投稿
- ステルスマーケティング
- 法律・法令違反
- ジェンダーや宗教、民族、イデオロギーなどに関する投稿
- 公式SNSの誤投稿
ユーザーを不快にさせる投稿としては、他人への誹謗中傷や、他社商品・サービスへの批判などがあります。また、ジェンダーや宗教といったセンシティブな内容の投稿も炎上を招く恐れがあります。インフルエンサーを起用した広告案件でありながらPRと書かれておらず「ユーザーを欺いている」行為はステルスマーケティングに該当し炎上リスクが高くなるため、ガイドラインを守るようにしましょう。
企業がSNSで炎上するまでの経過
企業がSNSで炎上する場合、多くは以下のような経過を辿ります。
- 投稿
- ユーザーが発見する
- 拡散される
- まとめサイトやネットニュースに掲載される
- サジェストに表示される
- テレビや新聞などのメディアに掲載される
- さらなる拡散と批判が殺到する
上記の流れは炎上元となる投稿があってから24時間以内に起こることが多いです。一度オンライン上にアップされたものはどんどん拡散されていくものですが、時間が経過するほど元の投稿や前後の文脈は見られないまま、まとめサイトやネットニュースを読んだだけの批判も加速度的に膨らんでいきます。
対応が遅ければさらに拡散と批判が大きくなっていくので、早期発見と的確な対応が肝心です。
▼炎上のメカニズムとは?SNSの基礎知識とリスク対策の取り組みはこちら
企業のSNSが炎上している際の対処方法
企業のSNSが炎上した際の対処には、「迅速な原因究明」、「関係各所との情報共有」、「真摯な対応」が不可欠です。各ポイントについて見ていきましょう。
迅速な原因究明
SNSでの炎上を早期に発見すると同時に、炎上原因を究明、正確に把握し、適切な対応策を練ることが大切です。
原因が分からないまま投稿を削除し、企業側の説明が不足していると、ユーザーの感情を逆撫で、さらなる批判に繋がってしまうでしょう。炎上原因の投稿はユーザーがスクリーンショットなどで保存しているため、削除後にもさらに拡散されていく可能性があります。
まずは、早期発見・原因究明が重要です。その上で素早い初期対応により、拡散や事態の悪化を最低限に抑えなければなりません。
関係各所との情報共有
炎上すると関係各所にも多大な影響を与えます。従業員や取引先、株主、クライアントなど関係各所に状況を共有した上で、対応の方向性を協議し、計画的に対処する必要があります。
対応を検討する際は法的な側面のみならず、SNS上のユーザーの論調もチェックし、世間の感覚とかけ離れないよう気を付けましょう。
炎上はいつ発生するか予測できず、関係各所と十分な協議ができない時間に起きることもあります。社内マニュアルを作成・共有しておき、いざという時にはガイドラインに沿って進めていくようにしましょう。
真摯な対応
関係各所に対しても、ユーザーに対しても、一貫性のある真摯な対応をすることが重要です。
対応に一貫性がないと不信感を抱かれてしまうため、社内で発信する内容を取り決め、周知した上で対応をするようにしましょう。
昨今ではSNSユーザーから過去に起きた類似の炎上事例に言及し「学びがない」、「反省がない」といった論調でさらに炎上が拡散するケースも増加しているため、過去の炎上事例を参考にすることも、炎上対策に有効です。
炎上を未然に防ぐための対策
一度炎上してしまうと、すぐに鎮火させるのは困難です。企業がSNSを活用する場合、炎上しないよう対策を講じておくことが大切です。ここでは、炎上を予防するための対策について紹介します。
社内での教育・研修
全従業員に対し、教育・研修の機会を設けましょう。SNS炎上のリスクや発信の基本的な姿勢、方向性などを教育するようにします。
教育・研修では各SNSのガイドラインを押さえて周知するのも良い方法です。例えば、Xのガイドラインには、「暴力的な発言」、「攻撃的な行為/嫌がらせ」、「ヘイト行為」など様々なものがあります。それらに抵触しないような指導が必要です。
▼SNSリスク研修を検討するときに!研修事例や成功のためのポイントを紹介
運用マニュアル・ガイドラインの策定
SNS更新に関わる部門で共有できる運用マニュアルを作り、策定したルールを厳守することで炎上リスクを低減できます。
他者に配慮した情報発信の基本原則のほか、ステルスマーケティングにならないようにするため、薬機法・景品表示法を遵守するためなど、自社の商材に合わせた具体的なルールを設定しておくことも重要です。
明確なマニュアルやガイドラインを策定することで、炎上防止に役立つだけでなく、炎上が起きた後の対応も速やかになり、初期対応のミスを防げます。
炎上事例の継続的な収集・分析
炎上が発生した際には、その内容を迅速かつ正確に把握し、適切な対策を取ることが重要です。そのためには、過去の炎上事例を収集・分析し、原因や影響、効果的だった対応策を整理しておく必要があります。特に同業他社の事例は、自社への参考になるため積極的に集めましょう。
また、炎上の原因は時代や社会の価値観の変化によって変わるため、継続的な情報収集も重要です。SNSのトレンドや世論の動きを常に注視し、炎上の兆候を早期に察知して事前に対策を講じることが望ましいでしょう。
ソーシャルリスニングサービスの導入
SNS上のリスクを常時監視し迅速な対応を可能にするためには、ソーシャルリスニングサービスの活用が効果的です。
X(旧Twitter)やInstagram、掲示板などの投稿を収集・分析するサービスを導入することで、オンライン上の動向を常に把握することができ、リスクの早期対応が可能になります。また、アラート機能を備えている場合は、より炎上へのスピーディーな対応ができるでしょう。
さらに、ツールによるデータ収集だけでなく、専門的な視点からリスクの重大性を判断し、対応策を助言するコンサルティングを組み合わせることで、より精度の高いリスク管理ができます。
デジタルリスクに備えるならエルテス
エルテスでは24時間365日、AIと人の目を介した「Webリスクモニタリング」サービスを提供しています。
お客様の課題に沿った最適なメディアやキーワードのご提案からシステムの反映まで、お客様の負担の少ない形でリスク検知体制を提供します。緊急性の高い投稿を検知した場合には、緊急通知や沈静化までの初期対応を支援しています。
SNSリスクの相談は、エルテスへ
まとめ
企業のSNSが炎上するケースは様々で、一度起こると事態の収集が難しく、企業イメージを大きく損なう場合もあります。炎上を絶対に起こさないようにするのは不可能だと言われていますが、これまでに起きた炎上事例を学び、対策を講じておくことは、炎上を防止する上で非常に大切です。
今回紹介した炎上事例のほかにも似たような事例はたくさんあります。同じことがないよう留意しながら、SNSモニタリングなども活用しつつSNSを運用していきましょう。