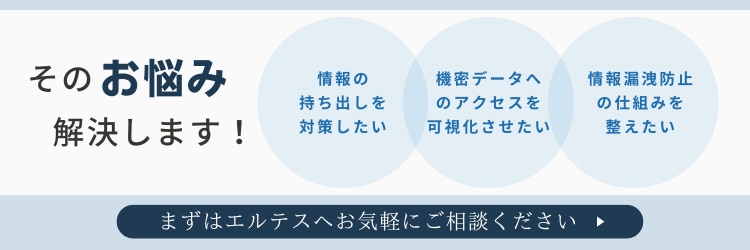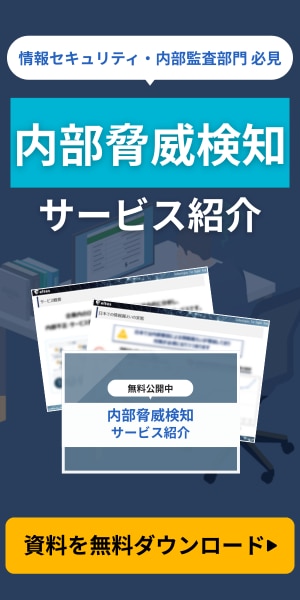振る舞い検知で内部リスクに備える|仕組みと企業での活用例を紹介
情報漏洩や内部不正など、企業を取り巻くセキュリティリスクが多様化・深刻化するなか、注目されているのが「振る舞い検知」です。
この記事では、振る舞い検知の概要や検知対象となる具体例、さらには企業の導入事例までをわかりやすく解説します。
自社のセキュリティ体制を見直したい、内部不正や情報漏洩を未然に防ぎたいと考えている企業の担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
ログ監視とは
まずは振る舞い検知を理解するうえで欠かせない基礎知識として、「ログ監視」の仕組みと役割について確認しておきましょう。
ログ監視とは、システムやアプリケーションが生成するログデータを監視し、不正アクセスや情報漏洩、システム障害などを早期に察知するためのプロセスです。
ログには、システムの利用状況やエラーメッセージなど、さまざまな詳細情報が記録されています。これらの情報を分析することで、システムの状態把握や障害原因の特定、リスクの兆候発見などが可能になります。
ログ監視の目的

ログ監視の目的は、「不正抑止」「予兆検知」「事後調査」の3つに大きく分けられます。それぞれ、企業における情報セキュリティ体制の構築やリスク管理において重要な役割を果たします。
不正抑止|見られているという意識がリスク行動を抑える
ログが常に記録・監視されていることが従業員に認知されることで、内部不正や情報の不正持ち出しといった行為を心理的に抑制できます。
「業務行動が可視化されている」という意識が働くことで、業務中の不用意な操作やルール違反を防ぐ効果が期待されます。
このように、ログ監視は技術的な検出だけでなく、人的リスクの抑止力としても機能する点が特徴です。
予兆検知|異変の兆しをログから察知する
日常的にログを収集・分析しておくことで、システムやネットワークの「通常時の動作パターン」を把握できるようになります。
これにより、普段とは異なる挙動や通信の変化など、異常の兆候に素早く気づくことができます。
たとえば、ログイン試行回数の急増や、業務時間外のアクセス増加、特定サーバーへの大量通信などが検知できれば、マルウェア感染や内部からの情報漏洩、DDoS攻撃の準備といったリスクを重大インシデントになる前の段階で検出・対処できる可能性が高まります。
つまり、ログ監視は「何かが起きた後」だけでなく、「何かが起きる前」の兆しを読み取るための有効な手段なのです。
事後調査|何が起きたかを証拠として遡れる
インシデント発生後の対応では、正確な原因特定や被害範囲の把握が求められます。
その際に、ログは「誰が・いつ・どこで・何をしたか」を示す証跡として、非常に重要です。
たとえば、不正アクセスや情報漏洩が発覚した際も、ログがあれば被疑者の特定、アクセス経路の解析、対応遅れの有無などを裏付けできます。
さらに、監査・説明責任・再発防止策にも活用でき、事後対応の正確性と信頼性を高める役割を果たします。
ログの記録内容
では、実際にログにはどのような情報が記録されているのでしょうか。ログの種類によって差はありますが、ここでは代表的な「アクセスログ」の記録項目を例に見ていきます。
項目 | 例 |
いつ | そのアクションが発生した日時 |
誰が | そのアクションを行った人、機器 |
何を | そのアクションが何に対して行われたのか |
どこで | そのアクションがどこで行われたか |
どうやって | そのアクションが、どのように行われたか |
どうなった | そのアクションの結果はどうだったか |
このようなログ情報は、システムの健全性や利用実態を把握するだけでなく、万が一のインシデント時における原因調査や被害範囲の特定、再発防止策の策定にも活用されます。
つまり、ログ監視は単に「記録を残す」ための仕組みではありません。企業のリスクマネジメントやコンプライアンス体制の中核を支える、戦略的なセキュリティ対策といえるのです。
振る舞い検知とは
ログ監視を発展させた手法として注目されているのが、「振る舞い検知」です。
振る舞い検知とは、あらかじめ定義されたシグネチャ(既知の脅威パターン)に頼るのではなく、「ユーザーやシステムの通常の振る舞い」から逸脱した行動をリアルタイムで検出するセキュリティ技術です。
結果として、情報漏えいやシステムの悪用といった問題の予兆を早くキャッチし、被害の拡大を防ぐことにつながります。
振る舞い検知の対象
振る舞い検知の対象となるのは、未知のマルウェアやネットワーク、ユーザーの異常な行動などです。ここからは、それぞれの具体例と検知の仕組みについて、以下で詳しく解説します。
未知のマルウェア・ウイルスの検知
振る舞い検知の代表的な活用例が、未知のマルウェアやウイルスによる異常な挙動の検出です。
これらのマルウェアは、既知のウイルスのようにシグネチャ(定義済みの脅威パターン)を持たないため、従来のパターンマッチング型の対策では検出が困難です。
しかし、振る舞い検知であれば、マルウェアが実行された際の異常なプロセスの起動や不自然なファイル改ざんなどをリアルタイムで監視・分析することで、侵入や感染の兆候を早期に捉えることができます。
特に重要なのがゼロデイ攻撃への対応です。これはソフトウェアの脆弱性が公開される前に行われる攻撃で、防御が極めて困難とされています。振る舞い検知はこうした未知の脅威にも有効であり、シグネチャ更新を待たずに脅威を察知できる点が大きな強みです。
ネットワーク上の異常な通信
振る舞い検知は、システム内部だけでなく、ネットワーク上の通信パターンの異常にも対応できます。
▶対象例
これらの兆候は、情報漏洩や遠隔操作ツールによる不正操作の前段階で発生する可能性があり、見逃すと被害が拡大するリスクがあります。
また、DDoS攻撃やブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)といった外部攻撃においても、通信の異常な変化を検出することが早期対応に役立ちます。
ユーザーの異常な行動
振る舞い検知は、従業員など内部ユーザーの不正や誤操作の兆候検出にも活用されます。
▶対象例
権限のないユーザーによる機密情報へのアクセス
これらはいずれも、内部不正や情報漏洩の前兆として現れるケースが多く、早期発見と対処が極めて重要です。
振る舞い検知は、ログ単体では見抜けないこうした異常な挙動をリアルタイムで検出し、内部リスクの可視化と抑止に大きく貢献します。
関連記事:エンドポイントセキュリティの重要性と選び方を徹底解説!
デジタルリスクに備えるならエルテス
振る舞い検知によって内部リスクに備えたい企業に向けて、エルテスが提供しているのが内部脅威検知サービス「Internal Risk Intelligence(IRI)」です。
IRIは、社内で発生する各種ログを横断的に分析することで、従業員の通常とは異なる振る舞いを可視化し、情報漏洩や不正行為の兆候をリアルタイムに検知することができます。
特徴は以下の通りです:
- 既存のログをそのまま活用でき、追加ソフトウェアの導入が不要
- ログの収集体制が未整備な企業に対しては、構築支援から対応可能
- 業務を逸脱した操作や、機密情報への不自然なアクセスを特定
これにより、従来のログ監視では見逃されがちなリスク行動を検知し、重大インシデントを未然に防止する体制を構築できます。
▶ 内部脅威検知サービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら
導入事例|企業における振る舞い検知の活用効果
・三菱UFJ eスマート証券株式会社様(金融業界)
社内のセキュリティリスク管理体制を強化する目的でIRIを導入された事例です。
導入前は、システムリスク管理グループや各部署の担当者が、膨大なログを目視で確認する作業に多くの時間を費やしており、作業負担が大きいことが課題となっていました。
IRI導入後は、膨大なログの分析を機械的に行えるようになり、確認作業を最小限に抑え、必要な場合にのみ現場担当者にヒアリングする運用へと効率化されました。
これにより、大幅な工数削減が実現し、現場の負担が軽減されました。
詳しくはこちら▶ https://eltes-solution.jp/case/case-11
・株式会社GRCS様(GRC・セキュリティ業界)
IPO準備にあたり、社内の脅威へのセキュリティレベルを強化する目的でIRIを導入された事例です。
導入後は、社内の全操作ログを常時分析できる体制が構築され、「社員の振る舞いを見える化」できるようになりました。
たとえば、届出のないUSB接続があった際には、IRIのアラートを通じて検知し、社員へのヒアリングが行える運用を継続されています。
これにより社内のセキュリティ意識が向上したほか、IPO審査では「IRIを導入して社員のリスクに繋がりうる振る舞いを検知し、分析・対策を行っています」と具体的に説明した結果、情報セキュリティに関する追加の質問は一切ありませんでした。
さらにISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)審査においても、IRIのレポートがルール遵守の確認資料として活用され、運用負担の軽減につながっています。
詳しくはこちら▶ https://eltes-solution.jp/case/case-17
振る舞い検知の相談は、エルテスへ
まとめ
振る舞い検知は、これまでのログ監視だけでは把握しきれなかった内部リスクを可視化し、情報漏洩や不正行為の予兆を早期に捉えるための有効な手段です。
今後、企業のセキュリティ対策においては、「異常が起きた後の対応」ではなく、「兆候を捉えて未然に防ぐ」ことがより重要になるでしょう。
少しでも不安や課題を感じているなら、まずは現状を見える化することから始めてみてはいかがでしょうか。
ぜひ一度エルテスへお気軽にご相談ください。