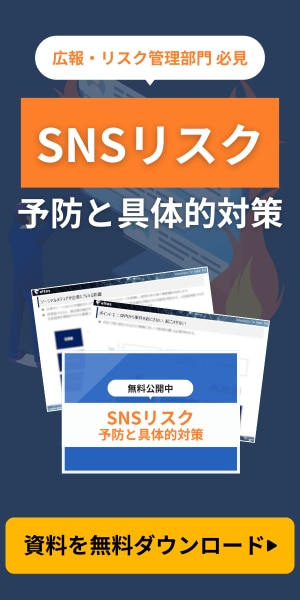中国進出を考える日本企業が押さえておきたいデジタルリスクとは
ビジネスを発展させるにあたり、市場選びは大事な要素の1つです。国内のみならず海外市場も検討することで、売り上げや利益の拡大が期待できます。その中でも近年で注目されているひとつが中国市場です。
マーケティング戦略としてWeibo(微博)やWeChat、そして近年注目度が高まるRED(小紅書)といった中国独自のSNSを活用する動きも盛んです。しかし、こうした中国SNSの活用には日本国内とは異なるデジタルリスクが存在し、対策が不可欠です。
今回は、中国独自のデジタルプラットフォームや中国進出を考えるうえで押さえておきたいデジタルリスクに焦点を当てて解説します。
目次[非表示]
なぜ日本企業が中国進出をするのか
世界第2位の経済大国である中国は、その巨大な市場規模で日本企業のビジネス拡大の舞台となっています。また、中国にとっても日本の製品は高いニーズが見込まれています。このような背景から、多くの日本企業が中国市場への進出を戦略的に進めています。
中国市場の規模の大きさ
中国は、国内総生産(GDP)が世界第2位の経済大国であり、人口も14億人以上の世界第2位を誇っています。この中国市場の規模の大きさが、日本企業が中国に進出する理由の1つです。事業を大きくしていくためには国内向けのみならず、さらなる成長が期待できる中国に進出していくのは、企業にとって有効な戦略と言えるでしょう。
さらに、中国国内にはビジネスチャンスに満ちた経済特区や開発区と呼ばれる魅力的なエリアがあります。こういった地域では企業所得税が数年免除されたり、様々な事業支援金が給付されたりと資金面で大きなメリットがあるため、多くの日本企業が制度を活用して中国進出を果たしています。
越境EC市場の大きさ
海外の代表的な越境ECサイトとしては、アメリカの「Amazon」や中国の「Tmall」などがあります。
中国の越境ECの市場規模の大きさも、日本企業が中国進出をする理由として挙げることができます。経済産業省の「令和4年度電子商取引に関する市場調査」によると、中国における2022年度の越境EC購入額は5兆68億円。また、中国消費者による日本企業からの購入額は2兆2,569億円であり、中国における越境ECの取引シェアのおよそ45%を日本が占めています。
日本の巨大なシェアのバックグラウンドには、中国国内では買えない製品のニーズがあるほか、日本製品の値段やクオリティ、ブランドに魅力を感じているユーザーが多いことが要因です。さらに、越境ECでは実店舗を持たなくて良いため、現地で出店するのに比べて出店コストや在庫リスクを抑えられるという利点があります。
このようなメリットの高さから、日本企業の中国市場は注目されています。
独自の発展を続ける中国のデジタルプラットフォーム

ネットが普及した近年では、日本を含め世界的にネットやSNSをビジネスに利用することが当たり前になってきています。一方で、中国は独自のデジタルプラットフォームを発展させていったため、中国進出を考えるうえでは押さえておくべき要素と言えます。ここでは、中国で有名なSNSやWebサービスを紹介します。
Weibo(微博/ウェイボー)
Weibo(微博/ウェイボー)は、X(旧Twitter)に相当するSNSです。中国国内で最も人気のあるSNSの1つで、短いテキストメッセージや写真、ビデオの投稿ができ、ユーザー同士のコミュニケーションやフォロー、シェア、コメントなどの機能があります。月間アクティブユーザー数は6億500万人(2023年9月時点)を超え、多くの人が情報収集やコミュニケーションに利用しています。
WeChat(微信/ウィーチャット)
WeChat(微信/ウィーチャット)は、中国最大のチャットアプリです。中国版LINEとして知られ、メッセンジャー、スタンプ、通話機能を備えています。月間アクティブユーザー数は2023年11月時点で13億人を超えています。ユーザー層は18~35歳が多いとされていますが、近頃は子どもや孫とやり取りをするために55歳以上の利用者も増えていると言われています。また、WeChatPayという電子機能もあり、多くの人が公共料金の支払いやショッピングに利用しています。
RED(小紅書/レッド)
RED(小紅書/シャオホンシュとも、通称「レッド」)は、中国で急成長している口コミ型SNSプラットフォームです。写真や動画を用いた商品レビューや体験談の投稿が人気を集めています。
その使い勝手やデザインから「中国版インスタグラム」と呼ばれるほか、アプリ内にEC機能やレビュー機能が備わっている点で「Instagram×Amazon」のような存在とも評されます。
実際、コスメやファッションをはじめ、旅行・グルメ・ライフハックの共有まで、多種多様な情報が日々投稿されています。ユーザーは気になった商品の投稿を閲覧し、口コミを参考にしてそのまま購入に至ることができるため、特にトレンドに敏感な若年層の女性を中心に絶大な支持を得ています。
さらに、投稿検索機能が充実しているため、検索エンジンの代わりにRED上で情報検索するユーザーも多く、重要な情報ソースとしても活用されています。
Taobao(淘宝/タオバオ)
Taobao(淘宝/タオバオ)は、中国EC事業のシェアトップを誇るアリババグループが2003年に設立したECプラットフォームです。CtoC(個人間取引)を軸としており、会員数が5億人を超えているショッピングモールです。
Tmall(天猫/ティーモール)
Tmall(天猫/ティーモール)は、Taobaoと同じアリババグループが運営するECサイトです。基本的にBtoCモデルで、Tmall Globalという越境ECプラットフォームがあります。徹底して偽造品や非正規品を排除しているため、非正規品が多く出回っている中国市場においてユーザーの信頼を獲得しています。
Baidu(百度/バイドゥ)
Baidu(百度/バイドゥ)は、中国最大の検索エンジンです。中国ではインターネット検閲があるため、Googleなど国外ネットサービスを自由に使うことができません。そのため中国生まれのBaiduが国内で絶大なシェアを持ち、中国の人々や企業にとって必要不可欠な検索エンジンとなっています。「百度文庫」という文書共有サイトもあります。
中国進出を目指す企業が気を付けたいデジタルリスク
中国マーケティングには欠かせない存在となっているSNSやECサイト。リスクを回避・低減しながら中国進出するには、どのようなことに気を付けたら良いのでしょうか。
ここでは、中国進出を目指す企業が気を付けたいデジタルリスクについて紹介します。
企業発信側のSNS炎上
独自のデジタルプラットフォームを持つ中国にも炎上リスクは存在します。
例えばWeiboは他の人の投稿にコメントしたりシェアしたりなど、XやFacebookと似た使い方がされるため、批判的な内容が拡散され炎上するリスクもあります。
また、日本では何気ない投稿でも中国の文化・歴史的背景などの配慮不足から、中国国内で敏感に反応され、炎上することがあるため注意が必要です。SNSで企業が批判を受けると不買運動に発展したり、謝罪や罰金を科せられるケースもあります。
他国でビジネスを行う企業は、その国の歴史をよく知り、現地の人の感情を害さないよう振る舞うことが基本です。中国進出をするうえでは「日本では今まではそれほど問題視されなかったことが、大きな問題として扱われるようになっている」という点を、危機管理として認識しておくべきでしょう。
従業員による情報漏洩
企業の従業員がプライベートで利用するSNSが思わぬ情報漏洩経路になる可能性にも注意が必要です。従業員がSNS上に自社に関する内部情報をうっかり投稿してしまったり、業務で使用した資料やデータを私的に共有してしまったりするケースです。
例えば、社内の営業資料や未公開の製品情報を、SNS上に無断で公開してしまうような事態が懸念されます。そのような投稿が拡散すれば、本来秘密であるべき情報が誰でも閲覧できる状態となり、企業に大きな損害を与えかねません。
企業としては従業員に対するSNSリテラシー教育を徹底し、社外秘情報を扱う際のルールを設けるなどの対策が不可欠です。
文書共有サイトでの情報漏洩
中国には「百度文庫」や「豆丁网(docin)」、「道客巴巴(DOC88)」といった文書共有サイト・サービスがあります。
文書共有サイトは誰でも自由にWord、Excel、PowerPointなどの電子データをアップロードでき、不特定多数がこれらを検索・閲覧・ダウンロードができるようになっています。
アップロードされている文書の中には「機密」、「Confidential」などと書かれた、企業で秘密情報としてきちんと管理されるべき資料も散見されていることが指摘されています。
サービスによっては、自身の資料をアップロードするとポイントを獲得でき、そのポイントを使用してサイト内の文書・資料をダウンロードできる仕組みになっています。文書をアップロードする動機が生まれやすいうえ、閲覧が可能になるため、情報漏洩が起きた場合は被害が拡大するリスクがあります。
SNSでの情報漏洩を防ぎたいならエルテス
中国市場でのデジタルリスク対策を含め、SNS上での炎上や情報漏洩を未然に防ぎたいとお考えでしたら、ぜひエルテスにご相談ください。
エルテスでは24時間365日、AIと人の目を介したSNSの監視・コンサルティングサービスを提供しています。お客様の課題に沿った最適なメディアやキーワードのご提案からシステムの反映まで、お客様の負担の少ない形でリスク検知体制を提供します。緊急性の高い投稿を検知した場合には、緊急通知や沈静化までの初期対応を支援しています。
まとめ
中国は日本からアクセスもしやすく、経済大国であることから、日本企業にとっても大きな可能性を秘めている市場です。中国進出を目指すことを考えている日本企業は、多くのメリットやビジネスチャンスに目を向けつつ、中国独自のデジタルリスクへの対策も行うことをおすすめします。
デジタルリスク対策の相談はエルテスへ