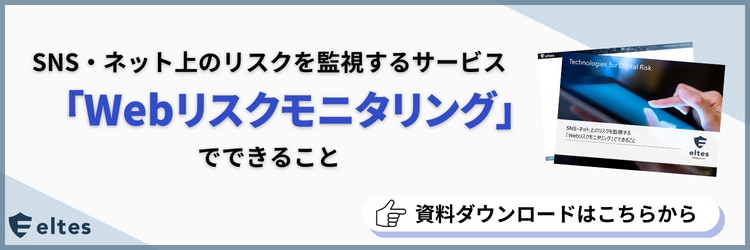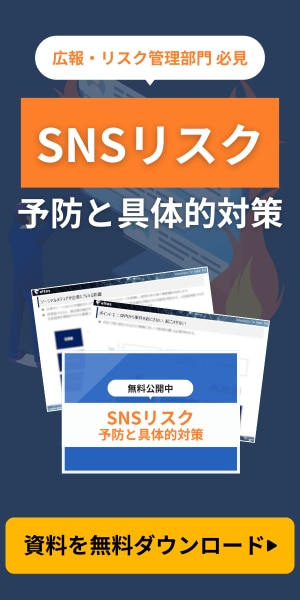大企業がSNSの使用を禁止することはできる?SNS監視の手順も徹底解説
SNSは便利な一方で、不適切な投稿が企業の信頼を揺るがすリスクを抱えています。情報漏洩や炎上を防ぐために、社員のSNS利用を制限・監視する大企業が増えています。この記事は、大企業がSNSを制限する理由やその対策について詳しく解説します。
▼【お役立ち資料】SNS監視の方法を詳しく知りたい方はこちら
目次[非表示]
大企業がSNSを禁止する理由とは?
社員のSNS利用を禁止する企業が現れる理由の一つに、投稿者個人の行動が組織全体の評価や信頼に大きく影響を与えるリスクがあるからということが考えられます。
不適切な投稿が拡散し、炎上に発展した場合、影響は投稿者本人にとどまらず、企業全体にダメージを与えることがあります。特に大企業は社員数が多いため、取引先や顧客の信頼を損なうリスクも高いと言えます。
▶【コラム】企業がSNSを活用する際の注意点はこちら
SNSを禁止・監視することは法的に可能?

企業が社員の勤務時間外におけるSNS利用を全面的に禁止することは、私生活への過度な干渉とみなされ、パワーハラスメントとして判断される可能性があります。
厚生労働省は職場のパワーハラスメントの1類型として「個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)」を挙げています。そのため、勤務時間外のSNS利用を制限することは、この「個の侵害」に該当する可能性があります。
ただし、企業には自社の施設を管理し、秩序を維持する権利があります。これを法律用語で「施設管理権」と呼びます。施設管理権に基づき、社内でのSNS利用が、業務の支障となるケースが想定される場合は、勤務時間中のSNS利用を制限することができます。
参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
SNSの監視が必要になるケースとは?
SNSで特に監視が必要になるのは、情報漏洩リスクが発生する場面です。その背景には、社員の油断や不注意が多く見られます。
例えば、以下のような事例があります。
- 業務中に撮影した写真に新製品の開発状況や取引先など重要な情報が映り込む
- プライベートで訪れた有名人の情報をSNSで投稿してしまう
社員に業務用としてSNSアカウントがある場合もリスク管理が重要です。適切に管理しなければ、私生活と業務が混在しやすく、次のような課題を引き起こす可能性があります。
- 社員の気の緩みを招いて、不適切な利用を助長する
- 社員個人の発信が、情報の受け手に企業の公式見解と誤解される
業務上でSNSを利用する場合、リスク管理の観点では公式アカウントとして新たに開設して企業が管理することをおすすめします。
大企業におけるSNS監視の手順
大企業において、社員のSNS利用がもたらすリスクを適切に管理することは、企業の信用を守るために不可欠と言えます。そのため、SNS監視を行う際には、明確な手順を踏むことが重要です。
監視対象とキーワードの設定
まず、企業は「何を監視するのか」を明確にし、リスク管理の観点から特に重要なSNSやウェブサイトを監視対象として選定します。
キーワードを設定する際には、自社のブランド名、製品名、サービス名に加え、情報漏洩や誹謗中傷など、リスクを早期に検知するためのキーワードを追加します。これにより、社員が不用意な投稿を行っていないかを確認できるため、社内外で発生するトラブルの未然防止に繋がります。
監視方法と頻度の決定
次に、「どのように監視するのか」を決める必要があります。SNSを監視する方法は、大きく分けて「目視」「外注」「ツール」の3つがあります。
監視方法を選ぶ際には、対象とするSNSやウェブサイトの最新情報のみを確認するのか、キーワードを設定して効率的に監視するのか、という考え方があります。また、人による目視で確認するのか、システムや専用ツールを活用するのか、なども踏まえて、企業に合った最適な方法を選びます。
▶【コラム】企業に合わせたSNS監視の方法はこちら
監視目的と活用方法の明確化
最後に、「なぜ監視するのか」という目的を明確にし、監視導入の際には社員への十分な配慮が必要です。
社員に「信頼されていない」と感じさせないためにも、監視の目的と範囲を具体的に示し、信頼関係を維持するための適切な運用が求められます。
社員の不満が蓄積すると、企業全体のパフォーマンスや評価に悪影響を及ぼす可能性があります。
大企業のSNS利用制限による影響と対策
上述のように、SNS監視は情報漏洩や炎上リスクを軽減する一方で、社員の働きやすさや企業イメージに悪影響を与える可能性もあります。これらのバランスを取るためには、以下の具体的な対策が不可欠です。
適切なSNSガイドラインを策定する
まず、SNS利用に関する明確なガイドラインを策定し、社員に周知徹底することが重要です。
ガイドラインには情報漏洩の防止や誹謗中傷の禁止、企業イメージを損なう発言への注意点を明確に盛り込み、社員がSNS利用時に適切な判断を下せる環境を整えなければなりません。
▶【コラム】ソーシャルメディアガイドライン策定のポイントはこちら
▶【コラム】社員向けSNSガイドラインによくある項目はこちら
社内体制を強化する
SNS利用に伴うリスクを低減するためには、社内体制の強化も欠かせません。
ガイドラインの作成後にeラーニングや研修を実施し、ルールの理解を促すことが重要です。同時に、専門部署や担当者を配置し、迅速に問題を発見し、対応できる仕組みを構築する必要もあります。
ただし、監視体制の強化が社員の反発を招く可能性もあるため、その進め方には十分な配慮が必要です。
社内で炎上事例を共有する
過去にSNSで起きた炎上事例を社内で共有し、社員のリテラシー向上を図ることもおすすめします。
定期的に企業で起こり得る炎上事例を取り上げ、その原因や防止策について議論する機会を設けることで、社員がSNSのリスクを再認識し、具体的な事例を通じて適切な行動を学ぶことができます。
炎上の多くはリテラシー不足が原因で発生しているため、こうした取り組みの継続によって社員の意識を高めることが期待できます。
ソーシャルリスニングを実施する
社員のSNSを監視するだけでなく、ソーシャルリスニングを導入し、SNS上の潜在的な問題を特定することも重要です。
ソーシャルリスニングを活用し、商品名や業界特有のキーワードを監視対象として設定することで、不適切な投稿やネガティブな情報がないかを調査できます。
導入する際には、監視作業や緊急時のアラートを自動化できる「ソーシャルリスニングツール」の利用もおすすめします。ツールを選ぶ際は、対応するSNSの種類やアラート機能、分析機能などを比較し、自社の目的に合ったものを選定することが重要です。
▶【コラム】ソーシャルリスニングツールの選び方についてはこちら
SNSリスク対策の成功事例

導入事例:株式会社ロック・フィールド様
導入サービス:Webリスクモニタリングサービス
導入前の課題
定期的に社内でSNSのモニタリングは行っていた一方で日々監視するほど行っておらず、社会的なSNSリスクの高まりや、リスクへの素早い対応が必要な中で、リスクヘッジや監視体制など自社体制の見直しが必要だった。
導入後の成果
- SNSへのネガティブな投稿だけでなく、ポジティブやニュートラルな投稿からも課題や改善点を発見し、具体的な施策に活用できるようになった。
- 緊急通知事案の際、迅速な情報共有と適切な対応で、大きな炎上を未然に防げる体制ができた。
- エルテスのコンサルタントから得た他社事例や最新情報を活用し、SNSリスク対策の規定や研修を整備することで、従業員への注意喚起が社内に浸透した。
▶【導入事例】株式会社ロック・フィールド様の導入事例はこちら
デジタルリスク対策ならエルテス
エルテスでは24時間365日、AIと人の目でSNSを監視する「Webリスクモニタリング」というサービスを提供しています。
お客様の課題に合わせた最適なメディア・キーワードの設定からシステム反映まで支援し、負担の少ないリスク検知体制を構築します。
機密情報の投稿や重大インシデントがSNSやWeb上に出回った際には緊急通知を行い、沈静化までの対応をサポートします。導入から運用まで、コンサルタントが支援するため、安心してご利用いただけます。
SNS監視の相談はエルテスへ
まとめ
大企業がSNSの使用を全面的に禁止することは難しいものの、適切なガイドラインの策定や監視体制の構築によってリスクの低減は可能です。
また、SNSリスク管理に取り組む姿勢を示すことで、社員の協力を得やすくなり、炎上や情報漏洩の未然防止につながります。
社員のSNS利用に関するリスク対策をご検討中の企業様はお気軽にエルテスへご相談ください。