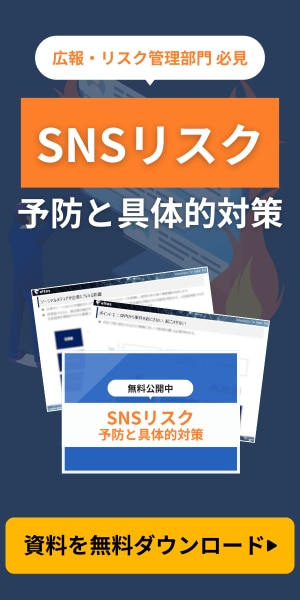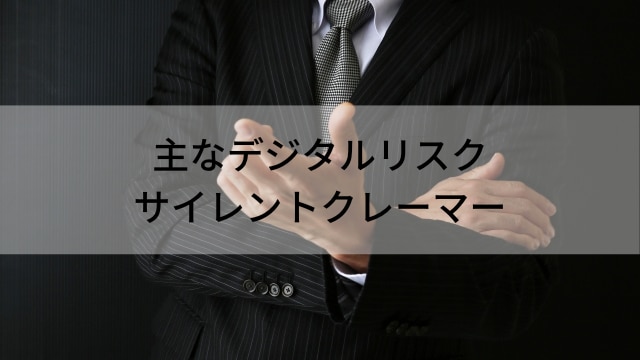
サイレントクレーマーとは?正しい対策方法を解説
目次[非表示]
▶クレームはSNS上にも浮上?SNSのクレーム対応のポイントを確認
サイレントクレーマーとは
クレーマーは一般的に、企業の商品や対応に対してしつこく苦情を申し立てる人を指します。お客様相談室などの開かれた窓口に対して、明確に要求を行うことから、その存在をはっきりと認識することができます。
しかし、サイレントクレームは異なります。サイレントクレームとは、「消費者や顧客が直接提供者に伝えないクレームのこと」です。そのようなクレームを企業に伝えずに、抱えたままのユーザーをサイレントクレーマーと言います。また、類似の属性として不満を伝えずに抱えたままのサイレントカスタマーと呼ばれるユーザーも存在します。
企業は、サイレントクレーマーが抱える不満を知ることが出来ません。しかし、消費者や顧客の抱える不満には、企業の成長のヒントが隠されていたり、サイレントクレームが炎上してレピュテーションの低下に繋がる可能性もあります。
2020年に日経リサーチと米国CCMC社が共同で実施した「生活者痛点基本調査 」によると、商品やサービスに不満を感じた日本人の割合は64.2%でした。そのうち、不満を企業に伝えたと回答した人はわずか27.5%にとどまっており、実に7割以上の人が、企業に何も言わずに不満を抱えたまま離れている実態が明らかになっています。
なぜサイレントクレーマー対策が必要なのか?
外部で拡散されるリスクがある
前述の調査では、企業に不満を伝えなかった人のうち、46.7%が「家族や知人に不満を話す」と回答しており、さらに21.7%が「SNSや口コミサイトに投稿する」と答えています。つまり、企業には何も言わなくても、消費者の不満は別の場所で発信されているということが分かります。
特にSNSなどのデジタル空間に不満が書き込まれてしまうと、SNS等を通じてサイレントクレームが伝播するリスクや、何年経っても批判がデジタル上に残り続ける可能性があります。
書き込まれたネガティブな口コミの影響力はポジティブな口コミの2~4倍にも達する とも言われ、サイレントクレームを放置することは潜在顧客や見込み顧客の獲得機会を失うリスクにもつながるのです。
こうしたリスクの実例として、過去に話題となった通販での提供商品トラブルの炎上事例の炎上騒動があります。これは、通販で届けられた料理の中身が、宣伝用の写真とは大きく異なり、量や見栄えに大きな差があったことが原因です。不満を抱いた顧客の多くは企業に直接クレームを伝えるのではなく、実際の商品画像とともにSNSや掲示板に不満の声を投稿しました。
その投稿が瞬く間に拡散され、提供元企業及び飲食店への非難が殺到して大きく炎上しました。企業側は後手の対応に終始してしまったことで信用の低下、サービス運営としても4年間の販売停止に追い込まれる事態にまで発展しました。
このケースは、サイレントクレームがSNS上に表出し企業に甚大な損害を与えた典型例と言えるでしょう。
▶重大なクレームが投稿されると?SNSのクレーム対応のポイントをチェック
改善のチャンスを逃すリスクがある
またクレームは企業にとって重大な機会損失にもつながります。クレームとして表面化しない不満は放置されがちですが、その中には自社製品やサービスの改善点であり、かつ顧客にとって優先度の高い課題が含まれていると考えられます。そのような改善点を野放しにしておくことは、ビジネス活動にとって、非常に大きな損失となり得ます。顧客ロイヤルティ協会の調査によると、サイレントクレーマーの90%以上は二度とその商品やサービスを利用しないとも言われており、不満を伝えてもらえない場合、企業は改善のチャンスも得られないまま大事な顧客を失っている可能性があります。
逆に、不満を持ったユーザーでも迅速に問題に対応し、ユーザーから高い満足度を得ることが出来れば、リピーターに繋がるという結果も出ています。
そこで、SNSをはじめとしたWeb上の顧客の声を積極的に収集し、能動的に不満に対応していくアクティブサポートを実施している企業も見られます。企業によっては、ソーシャルリスニングという言葉を用いて、実質的にアクティブサポートを行っているケースもあります。
具体的な運用方法や、企業が実際にどのようにWeb上の声を活用しているかについては、以下のコラムで詳しく解説しています。
▶ソーシャルリスニングとは?注目される背景とメリット
▶ソーシャルリスニングツールとは?企業のSNS担当者が知っておくべき活用法
サイレントクレーマー対策方法
サイレントクレーマー対策を考える際に重要なことは、どのようにすればサイレントクレーマーを減少させるかという視点です。そこで考えられるのは、下記の3つになります。
- お問い合わせフォームの設置やよくある質問(FAQ)の公開
- 不満を生まないサービス提供
- 情報発信の強化(不満改善を行える方法を知ってもらう)
しかし、一定数以上の表面化しないクレームは存在し、SNSや口コミサイトに書き込まれることは、やむを得ません。そこで重要になるのが、企業名やサービス名が分かる形で投稿されている不満を早期に検知し、適切に対処する仕組みです。
SNSや掲示板、レビューサイト上に自社名や商品名とともに投稿された不満や苦情の声を見逃さずキャッチできれば、フォローアップ対応や問題箇所の迅速な改善につなげることができます。投稿された不満が大きく広がる前に手を打つことができれば、炎上や評価低下のリスクを抑えられるだけでなく、顧客の信頼回復にもなり得ます。
エルテスの提供するSNS監視サービス
エルテスでは、Web上のリスク投稿を24時間365日監視するサービスを提供しており、その中で確認されたサイレントクレームを通知することも可能です。そのような顧客の声を早期に検知することで、リコール事案にも早期に気づき、大きな被害を最小化出来る可能性もあります。
また、24時間365日モニタリングを行うほどの投稿量がない場合や自社サービスに関するユーザーの声が大量にSNS上に転がっている企業の場合は、SNS上の論調把握をレポート化するオンラインレピュテーション調査という形で、レポート化して、納品することが可能です。
広いデジタル空間の片隅に転がっているリスクを早期に発見し、リスクを企業成長のチャンスに変えることが出来るかは、企業の顧客への向き合い方に左右されます。ぜひ、サイレントクレームというリスクをチャンスに変えられるような取り組みを行ってみてください。
サイレントクレーム対策は、エルテスへ
【関連情報】
〇関連資料
〇エルテスのサービス
〇関連コラム
・風評被害とは?企業の風評被害対策を状況別にわかりやすく解説