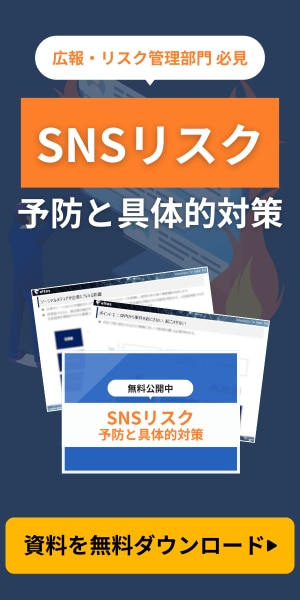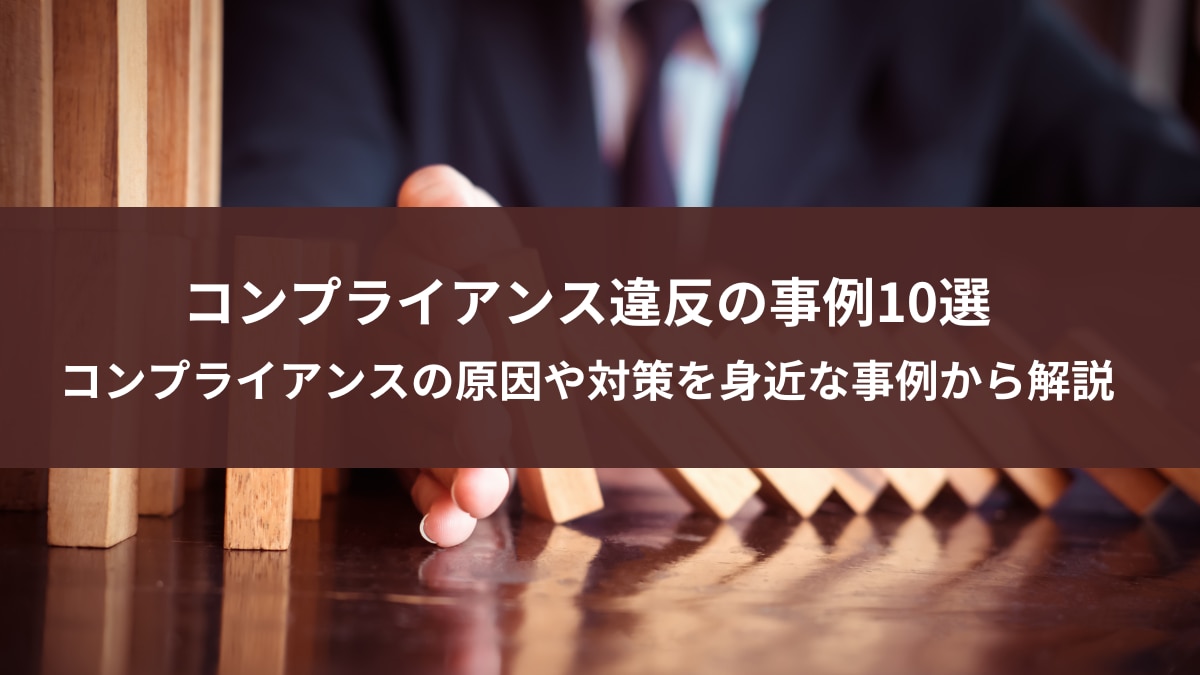
コンプライアンス違反の事例10選|コンプライアンスの原因や対策を身近な事例から解説
企業がこれまで積み重ねてきた価値や信頼を一瞬で失う可能性があるのが、コンプライアンス違反です。法令違反や社内ルール違反、個人情報の不適切な取り扱いなど、コンプライアンス問題は特定の業界や企業だけの話ではなく、非常に身近な事例として多く発生しています。
このコラムでは、コンプライアンスの基本から、企業や個人が実際に直面したコンプライアンス違反の事例を業界別に紹介し、違反が起きる原因と企業が取るべき実践的な対策、教育の重要性までを分かりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.コンプライアンス違反とは?
- 2.企業のコンプライアンス違反事例10選
- 2.1.<旅行業界>全国旅行支援の不正請求
- 2.2.<飲食業界>新型コロナウイルスの雇用調整助成金を不正に受給
- 2.3.<卸売業界>修理費用の水増し請求
- 2.4.<製薬業界>医薬品の異成分混入
- 2.5.<金融業界>顧客の個人情報を不正に利用
- 2.6.<通信業界>グループ企業による顧客情報漏洩
- 2.7.<公的機関>県職員によるセクハラ・県警察本部でのパワハラ
- 2.8.<広告業界>長時間労働による過労死
- 2.9.<小売業界>SNSのイラストを無断使用
- 2.10.<飲食業界>悪ふざけの動画投稿による炎上
- 3.従業員が引き起こすコンプライアンス違反事例
- 3.1.会社の備品・設備の私的利用
- 3.2.無許可でのデータ持ち出し・データコピー
- 3.3.経費の水増し
- 4.コンプライアンス違反が起きる3つの原因
- 5.コンプライアンス違反による悪影響
- 5.1.ブランド毀損・企業の信頼が失われる
- 5.2.法令違反による行政処分
- 5.3.損害賠償を請求される
- 6.コンプライアンスの違反事例から学ぶ防止策とは
- 7.デジタル空間におけるコンプライアンス違反
- 8.まとめ
▶【お役立ち資料】SNSで起きるコンプライアンス違反の対策はこちら
コンプライアンス違反とは?
企業における「コンプライアンス」とは、法令をはじめ、社内規則や社会的倫理を遵守しながら事業活動を行うことを指します。つまり「コンプライアンス違反」とは、法律違反に限らず、社内ルール違反や社会的に不適切と判断される不正行為全般の意味を持ちます。
コーポレートガバナンスやCSRとコンプライアンスの違い
コンプライアンスに似た用語の一つに「コーポレートガバナンス」がありますが、これは直訳で「企業統治」という意味を持ちます。金融庁と東京証券取引所が上場企業向けに定めた規定である「コーポレートガバナンス・コード」では、「企業が、株主や顧客、従業員、地域社会などの立場を踏まえた上で、公正・透明に、またスピーディーかつ果断に意思決定を行うための仕組み」と定義されています。
つまり、コンプライアンスはコーポレートガバナンスの一つの要素として組み込まれているため、違反が起きた時には、コーポレートガバナンスの問題としてとらえられる場合があります。
また、コンプライアンス関連のニュースなどでは、「CSR」という言葉もよく聞きますが、CSRは「Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任」という意味を持ちます。企業に対し、環境や次世代へ配慮しながら地域社会などへ責任をもって行動し、説明責任を果たすことを求める考え方です。
CSRを含む企業活動の前提となるものがコンプライアンスであり、企業の社会的責任を果たすには、コンプライアンスへの取り組みが欠かせないとも言えます。
企業のコンプライアンス違反事例10選
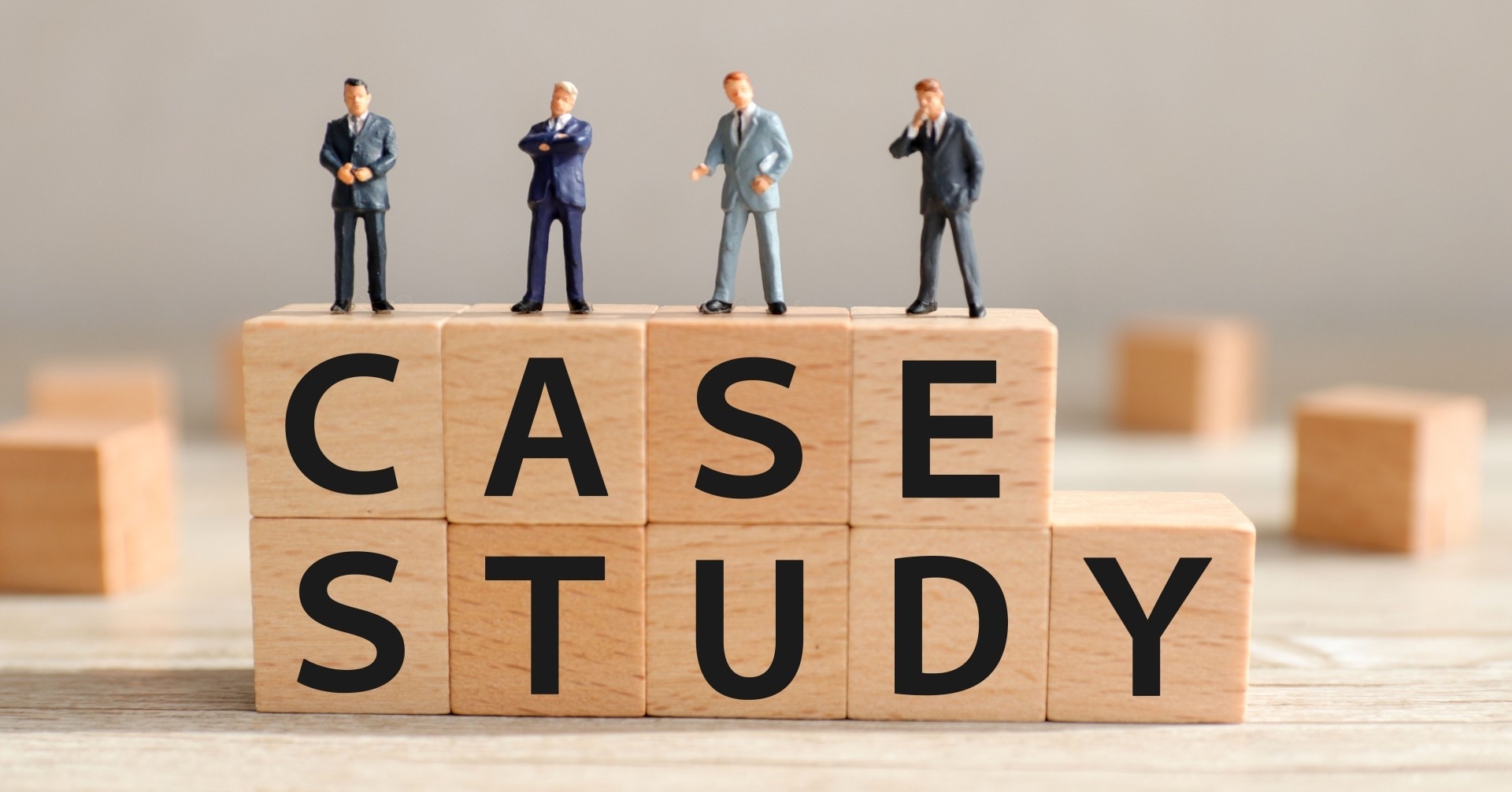
では、実際にどのようなコンプライアンス違反が起きているのでしょうか。ここでは、様々な業界で起きた身近なコンプライアンス違反の10事例を紹介します。
<旅行業界>全国旅行支援の不正請求
旅行業界の大手企業が、自治体から委託された全国旅行支援事業において、勤務実態のない人件費として約530万円を不正請求していた事例です。本来は1日あたり10~15人が勤務する契約でしたが、実際には「勤務実態のないスタッフのタイムカードを作成する」「人件費の安い外部派遣会社へ形式的に業務委託する」といった不正行為が行われていました。
<飲食業界>新型コロナウイルスの雇用調整助成金を不正に受給
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けに支給された雇用調整助成金を、居酒屋を運営する企業が不正に受給していた事例です。本来は従業員を休業させ、休業手当を支払った場合に支給される制度ですが、実際には感染者がいない、または給与を支払っていないにもかかわらず虚偽の申請が行われていました。
<卸売業界>修理費用の水増し請求
中古車販売会社が、顧客から預かった車両を故意に損傷させ、修理費用を水増しして損害保険会社へ請求していた事例です。保険金詐欺に該当する重大な法令違反であり、不正を認識していた疑いのある関連会社まで金融庁から立ち入り検査されるという事態にまで発展しました。
<製薬業界>医薬品の異成分混入
大手製薬会社において、国に承認されていない製造工程を用いた結果、真菌症を治療する薬に睡眠導入剤の成分が混入し、健康被害が発生した事例です。240人以上が健康被害を受けるという深刻な結果を招き、薬機法などの法令違反に該当し、自治体から業務改善命令と116日間の業務停止命令という重い行政処分が下されました。業務停止命令の後も製造・販売を再開することはなく、他の大手薬品企業に工場などを譲渡する結果となりました。
<金融業界>顧客の個人情報を不正に利用
大手金融機関が、顧客の個人情報を本人の同意なくグループ会社や証券会社と共有し、金融商品の勧誘に利用していた事例です。この行為は金融商品取引法などに違反している疑いがあったため、証券取引等監視委員会は対象の銀行3社に対し行政処分を勧告する方針を示しました。
<通信業界>グループ企業による顧客情報漏洩
大手通信会社のグループ企業に所属する元派遣従業員が、約900万件に及ぶ顧客の個人情報を不正に持ち出していた事例です。社内サーバーへのアクセス権限管理が不十分だったため、データへの不正アクセスは10年ほどにわたっていました。
<公的機関>県職員によるセクハラ・県警察本部でのパワハラ
公的機関における、職員によるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントが発覚した事例です。ある県の地域県政総合センターでは、男性職員が女性職員に対し勤務時間中に繰り返し性的な発言をするなど、セクシュアルハラスメントで懲戒処分を受けました。また、別の県の県警察でも、体罰や大声での叱責、悪口や嫌がらせ、無視、育児休暇取得の遠回しな拒否、アルコールハラスメントなどのハラスメント行為が判明しています。
<広告業界>長時間労働による過労死
大手広告代理店に入社したばかりの女性従業員が慢性的な長時間労働に陥り、過労で精神を病んだ末に自死へと追い込まれた事例です。裁判では企業の安全配慮義務違反が認められ、1億6,800万円の賠償命令が下されました。
<小売業界>SNSのイラストを無断使用
大手小売企業のデザイナーが、個人のSNSに投稿された画像を勝手に広告に使ってしまい、炎上した事例です。こうした無断使用は、作者本人やファンが気づいて指摘することで発覚するケースがほとんどです。「少し加工すれば大丈夫だろう」と思っても、著作権違反になる恐れがあります。
<飲食業界>悪ふざけの動画投稿による炎上
飲食店のアルバイト従業員が、店舗内で不適切な行為を撮影しSNSに投稿したことで炎上した事例です。動画では、アルバイト従業員が店内でホイップクリームを直接口に流し込まれる様子が映っており、SNSでは衛生面への懸念や店の管理体制への指摘が相次ぎました。
従業員によるSNS投稿は、個人情報の流出やブランド毀損につながる可能性があり、企業のコンプライアンス問題として捉える必要があります。SNSが普及した現代社会において、アルバイトの不適切行為は「バイトテロ」とも呼ばれメディアでも取り上げられるほどの社会問題です。再発防止には、アルバイトを含む全従業員に対して、SNS利用に関するルールやリスクを明確に伝える教育が不可欠であり、社内での注意喚起や定期的な研修が必要です。
従業員が引き起こすコンプライアンス違反事例
個人が気づかないうちに起こしてしまうコンプライアンス違反も存在します。ここでは個人によって引き起こされる可能性があるコンプライアンス違反を3つ紹介します。
会社の備品・設備の私的利用
個人が起こしがちなコンプライアンス違反の一例として、社内設備・備品の私的利用が挙げられます。企業では、仕事上で必要な備品・設備は従業員が自由に使用できるようになっていることが多いです。こうした備品・設備を業務で使うのは問題ありませんが、私的に利用するとコンプライアンス違反となるため注意しましょう。
具体例としては「会社で使う筆記具を自宅に持ち帰って使う」という行為はコンプライアンス違反に該当する可能性があります。「この程度であれば問題ないだろう」と個人が勝手に判断してしまうケースが多く、従業員の意識改革が必要となるケースです。
無許可でのデータ持ち出し・データコピー
会社の許可を得ることなく、会社が保有する個人情報や企業秘密などをコピーする・持ち出すなどの行為もコンプライアンス違反に当てはまります。
データのコピー・持ち出しの中でも顕著なのは「社外で業務を進めるため」という理由から悪気なくデータを持ち出すというケースです。USBメモリへのコピーやクラウドへの保存などもコンプライアンス違反となります。業務上の必要からデータを持ち出す場合は社内のセキュリティルールを遵守し、必要であればコピー・持ち出しの許可を取りましょう。
経費の水増し
経費の水増しも個人が引き起こしがちなコンプライアンス違反の一つです。経費の金額を正しく計算せず、誤った金額で経費計上してしまうなどの行為が当てはまります。
また、業務に関係のない物品などを経費に計上する行為もコンプライアンス違反となります。具体的には「同僚との飲食を得意先との接待と称して経費計上する」などの行為が経費の水増しとみなされます。何が経費となるのかは企業によって判断基準が曖昧である場合も多く、個人の判断で違反してしまうこともあるため、自己判断ではなく、事前の確認が重要です。
コンプライアンス違反が起きる3つの原因
コンプライアンス違反は知識不足、社内体制の問題などから起こるため、コンプライアンス違反が起こりやすい環境を形成しないことが重要です。
ここではコンプライアンス違反が起きる3つの原因を紹介します。
経営層・従業員のコンプライアンス関連の知識不足
社内規則や法令、社会倫理などの正しい知識がなければルールを守ることも叶いません。従業員はもちろん、企業の経営層も同様です。「コンプライアンスとはどういったものか」「なぜコンプライアンスに違反してはならないか」を十分に周知する必要があります。、また、どのような事柄がコンプライアンス違反に該当するか具体的に知り、理解を深めることも大切です。
コンプライアンス関連の基礎知識が十分でないために、気づかない間にコンプライアンス違反をしているケースもあります。たとえば、労務管理の場面で「最低賃金が上がっていたのを知らなかった」「育児休暇の取得は会社として拒否できると思っていた」などの事象が発生することがあります。
働き方や規範意識のアップデート不足
「入社年次・年齢が高い」「役職者である」などであれば、なおさら働き方や規範意識をアップデートするという意識を持つ必要があります。「昔は当たり前だったことでも現代ではコンプライアンス違反に当てはまる」ということはよくある話です。
コンプライアンス対策で言われる「社内規則」「法令」「社会倫理」などはいずれも永続的なものではありません。法令は逐次アップデートされ、社内規則も時代の変化や法令改正に即して変わりゆくものです。社会倫理に明確な基準はありませんが、人権意識や環境などへの倫理観は時代とともに変化します。こうした変化に対応できていなければ、気づかないうちにコンプライアンスに反する言動をしてしまう可能性があります。
また、規範意識やモラルが欠けていると、ハラスメント行為、個人情報の流出、SNSの炎上が発生しやすくなります。「多分バレないだろう」と他人の作品を盗作する、「面白いからOK」と悪ふざけしている動画をSNSにアップするのは、モラルの欠如による行為です。
コンプライアンス違反を防止する体制ができていない
コンプライアンス違反を防ぐには、前もって会社として予防する体制を整えておくことが大切です。仮に、法改正ごとに管理体制を見直す企業と、何も対策を講じていない企業を比較した場合、後者の方がコンプライアンス違反のリスクが高くなるのは容易に想像できます。
従業員の意識に頼るだけではコンプライアンス違反の予防効果は限定的です。コンプライアンス違反に関する明確な指針を設けて、コンプライアンス遵守の体制を整えることが企業に求められる取り組みです。
コンプライアンス違反による悪影響
コンプライアンス違反を起こした企業は、多大な影響や様々なリスクを背負うことがあります。ここではコンプライアンス違反による悪影響の例を3つご紹介します。
ブランド毀損・企業の信頼が失われる
コンプライアンス問題における最大のデメリットは、企業のブランドイメージが毀損され、社会的な信用を失うことです。
現代社会ではSNSが広く普及しており、コンプライアンス違反が社会に大きく影響を及ぼす内容であった場合、ネット上で炎上に発展するケースも多く見られます。ひとたび炎上すれば瞬く間に注目が集まり、それまで興味を持たなかった消費者もその不祥事に関心を持ちやすくなります。これにより、企業の信頼度は加速して低下する恐れがあります。
法令違反による行政処分
景品表示法、下請法といった企業が遵守しなければならない法律は数多くありますが、もし刑法に触れるコンプライアンス違反が起きた場合、重い行政処分が下されることもあります。
時には当事者が逮捕され、社内に家宅捜索が入るケースもあり得ます。たった一人の従業員が起こした違反であっても企業の管理不足とみなされ、管理責任を問われる場合があるので注意しましょう。
損害賠償を請求される
人命に関わるような内容のコンプライアンス違反の場合、遺族から損害賠償を請求され、提訴されることもあります。
たとえば、パワハラが発覚した場合の損害賠償は本人や企業に各30~100万円ほどの金額が請求されるといわれています。また、未払いの残業代などがあれば、さらに損害賠償の金額が上がります。内容次第では経営に影響するほどの賠償金が課される恐れもあります。
コンプライアンスの違反事例から学ぶ防止策とは
コンプライアンスの違反事例から学ぶことは多くあります。違反を防ぐためには、どのような策を講じればいいのでしょうか。

研修などを通じた従業員への定期的な周知
企業では、従業員に対してコンプライアンス違反対策を行うことが必要不可欠です。社内研修・勉強会を定期的に実施することにより、コンプライアンスへの意識が向上します。社外から講師を招いてもいいですし、グループワークを含む参加型にするとより効果が高まるでしょう。
通報窓口・相談窓口の設置
コンプライアンス違反が起きた時に、従業員が内部告発をするための通報窓口・相談窓口を設置しておくことも大切です。従業員が安心して相談・通報できるよう、匿名にしたり、責任の所在をはっきりさせるなど、第三者の目線を入れた透明性のある体制を整えましょう。
マニュアルやルールを定め、浸透させる
まずは、コンプライアンス違反につながりそうなリスクを洗い出し、対策するべき課題を把握します。そして、対策を社内マニュアルに記載し、すべての従業員に浸透させましょう。全社メールやポスターなどで周知を徹底することにより、未然に違反を防ぐことができます。
従業員アンケートや定期的な人事面談を通じて従業員のメンタルケア
従業員アンケートの実施も、コンプライアンス違反を防ぐために有効な手段です。
特に、次のような項目を調査するといいでしょう。
- 上司に知らせず時間外労働をしていないか
- 社外秘データを持ち出していないか
- 業務への不満や精神的疲れはないか
- 自社のコンプライアンスに関するルールで不明点はないか など
また、定期的な人事面談により、従業員一人ひとりの精神面のケアを行っていくことも大切です。
デジタル空間におけるコンプライアンス違反
昨今は、SNSなどデジタル空間におけるコンプライアンス違反も見られています。また、違反となるような言動がSNSにアップされ、拡散されることもあります。すでに、コンプライアンスに関する研修を行っている企業も多いでしょう。しかし、重要なのは、最新のコンプライアンス違反事例などを取り入れた研修を実施することです。
企業や従業員を守るためにも、時代に即したルールにアップデートできているかを都度確認することが必要になります。
▶【お役立ち資料】SNSで起きるコンプライアンス違反の対策はこちら
まとめ
コンプライアンス違反のリスクは、想像以上に身近に存在しています。
企業のブランド毀損や経営破綻につながりかねないため、「知らなかった」では済まされません。気づかないうちにコンプライアンス違反を起こさないよう、担当者は細心の注意を払う必要があります。
従業員一人ひとりのコンプライアンスに対する意識を高めるための取り組みを行い、コンプライアンス違反のリスクを減らしていきましょう。
コンプライアンス対策の相談は、エルテスへ