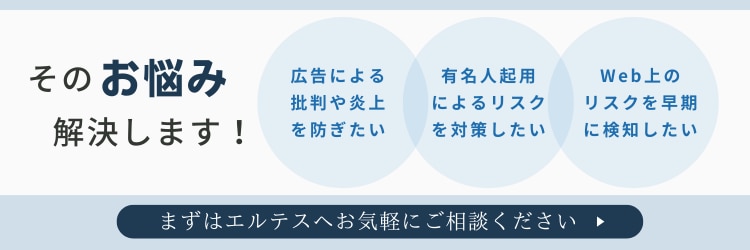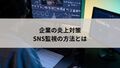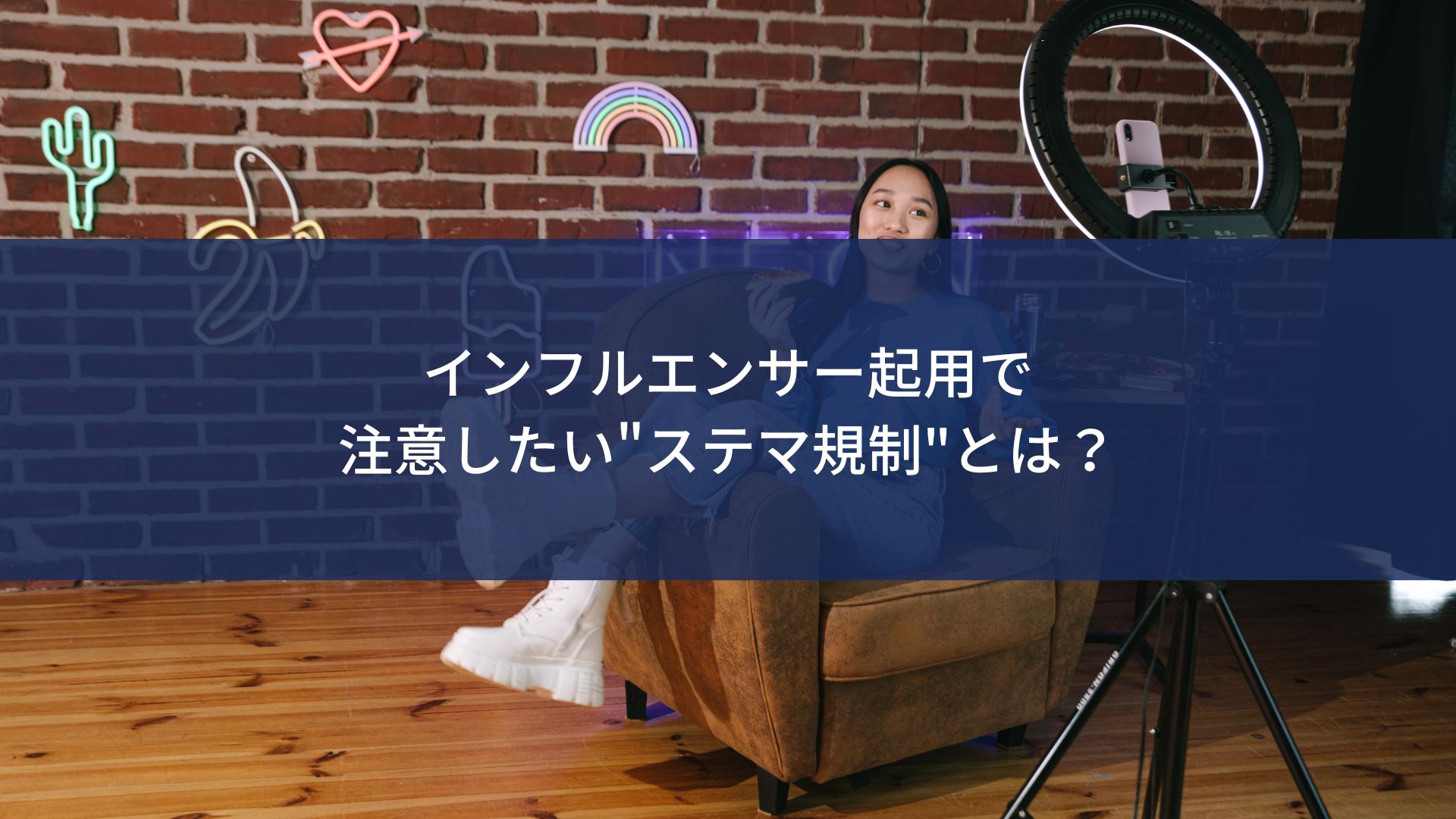
インフルエンサーマーケティングで注意したい「ステマ規制」のポイントと対策方針
ステルスマーケティング(ステマ)は消費者の正しい判断を阻むものであるとして、規制が強化されています。そのため企業やインフルエンサーは法令遵守するために、ステマ規制に関連する知識を持つことが求められています。本コラムではステマが発生した背景から、ステマにならないための対策などを解説します。
目次[非表示]
- 1.ステマは法律違反?「ステマ規制」とは何か
- 2.ステマが増加した背景
- 3.ステマ規制が強化された背景
- 4.ステマの何が違反対象となるのか
- 5.インフルエンサー活用の実態
- 6.なぜインフルエンサーマーケティングが拡大するのか?
- 7.企業がインフルエンサー起用時に注意すべき「ステマ」とは?
- 8.過去に行われたステマの事例
- 9.ステマにならないために押さえるべきポイントは?
- 10.ステマにならないSNS投稿
- 10.1.YouTube
- 10.2.Instagram
- 10.3.TikTok
- 10.4.X(旧Twitter)
- 10.5.Twitch
- 11.インフルエンサー起用時の注意点
- 12.まとめ
- 13.関連情報
ステマは法律違反?「ステマ規制」とは何か
2022年12月に消費者庁の検討会では「ステルスマーケティングを規制する必要がある」という内容を報告書にまとめました。これを受けて、2023年3月にはステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定すると告示しました。この新たな規制が施行される2023年10月1日からはステマは景品表示法の法律違反に該当します。
企業が特に注目すべき点は、インフルエンサーが誤って不当表示を行ってしまった場合でも責任に問われるのが広告主の企業ということです。2023年3月の告示の段階では不当表示に当たる基準として「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準が公開されています。
ステマが増加した背景
ステルスマーケティングという言葉が浸透したきっかけは、2012年に起こったペニーオークション詐欺事件と言われています。(芸能人やタレントが事業者から報酬を受け取り、落札していないにも関わらず落札したかのように装いブログで紹介した事件。)
その後、X(旧Twitter)を始めとしたSNSの利用が増加したことで、企業のマーケティングにおいてSNS上の感想や評価が重要視される傾向が強くなりました。
その中でも、多くのファンを持つインフルエンサーに商品やサービスを宣伝してもらう「インフルエンサーマーケティング」はマーケティング手法として地位を確立しました。
しかしSNSで、企業に依頼されて投稿していることがファンにわかると、「このインフルエンサーは、お金のために動いているのではないか」「本当に好きな商品ではないのではないか」といようなネガティブな印象を与えるリスクが懸念されました。
こうした背景から、広告であることを明示しない投稿が増え、ステマが問題視されるようになったと考えられます。
ステマ規制が強化された背景

消費者は企業が発信している広告に対して、宣伝のためにある程度誇張しているものと認識しています。その上で、消費者自身の判断に基づいて商品やサービスを選択することが一般的になっています。
しかし、広告であることがわかりにくい場合、消費者はそれを企業の発信物ではなく、第三者の率直な感想や評価であると誤った認識をしてしまう可能性があります。このような誤認が発生すると、判断基準が歪められ消費者が正しい意思決定ができないおそれがあります。
こうした背景から、広告や宣伝であることを隠す行為であるステルスマーケティングを防止するため、消費者庁は2023年10月より新たに規制を設けました。
ステマの何が違反対象となるのか
ステマが問題視されている点は、消費者に誤解を与えることです。そのため、広告であることが明確にわからない表示や、消費者の誤認を誘発するような表示は違反対象になります。例えば、「広告」や「PR」などの文言が記載されていない、記載されていてもわかりにくい場所にあるといった場合は、違反となる可能性があります。
また、規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。事業者から依頼を受けて、広告の制作や掲載、投稿などを行っただけのインフルエンサー・アフィリエイター・広告代理店など、第三者は規制の対象外となります。
インフルエンサー活用の実態

近年、YouTube、Instagram、X(旧Twitter)などSNSで多くの登録者やフォロワーを獲得し、芸能人と並ぶほどの影響力を持つインフルエンサーが何人も登場しています。
インフルエンサーの増加に伴い、インフルエンサーを起用する企業数も増加しています。株式会社サイバーエージェントが2018年に国内の広告主企業を対象にマーケティング活動におけるインフルエンサーの活用実態に関するアンケート調査を行ったところ、56%の企業がSNSやWebで影響力を持つインフルエンサーを活用したマーケティングを実施していることが明らかになりました。
インフルエンサー市場はさらに拡大を続け、2022年の株式会社サイバー・バズと株式会社デジタルインファクトによる共同調査によると、インフルエンサーマーケティングの市場規模は2020年に332億円でしたが、2023年には741億円になると推測されます。また、2027年には2023年比で約1.8倍の1,302億円にまで市場が拡大すると予測されています。
なぜインフルエンサーマーケティングが拡大するのか?
インフルエンサーを起用する企業が増え、インフルエンサーマーケティングの市場規模が拡大している理由はインフルエンサーの影響力の大きさにあります。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査によると、約55%ものSNSユーザーがインフルエンサーの投稿に影響されて商品やサービスを購入した経験があると回答しています。また、インフルエンサーの投稿に基づき購入した商品・サービスの満足度を問う質問では、94%もの人が「満足できるものであることが多い」と回答しました。
このように、SNSユーザーがインフルエンサーから受ける影響は大きいことに加え、満足のいく買い物ができるため、今後もインフルエンサーの影響力やユーザーからの支持は拡大していくと予想されます。
企業がインフルエンサー起用時に注意すべき「ステマ」とは?
今後商品やサービスのプロモーション活動に欠かすことが出来ないと考えられるインフルエンサーマーケティングですが、投稿の仕方やSNS上での振る舞いを間違えてしまうと炎上やトラブルにつながり、企業の評判を下げる可能性もあります。企業がインフルエンサーを起用することは非常に有効なマーケティング手法の一つですが、特に起用時に注意しなければならないのがステルスマーケティング(ステマ)です。
ステマとは、消費者に広告・宣伝であるにもかかわらず、それを明記せずに商品を宣伝する内容をSNSなどに投稿することを言います。企業の介在し宣伝が目的であることを隠して行われるため消費者を騙す側面があるとして、発覚すると炎上につながります。
過去に行われたステマの事例
次に、過去に実際に起こったステマの事例を紹介します。
某動画投稿プラットフォームの運営会社では、長期間にわたり影響力のある複数のインフルエンサーに報酬を支払い、指定した動画を一般の投稿かのように紹介させていたことが発覚しました。運営会社から投稿を依頼されたあるインフルエンサーは、1人で年間2000本以上の動画を投稿し、再生回数の合計が1億回を超えるケースもありました。
ステマにならないために押さえるべきポイントは?
ステマにならないために押さえるべきポイントとして、「関係性を明示すること」が挙げられます。
関係性の明示には、以下の2つの要素があります。
- マーケティング主体の名称
事業者の名前(企業の名前)、もしくはブランド名などを明らかにする。 - 関係の内容
広告であることを明らかにする。例えば、「広告」「プロモーション」「宣伝」などの、一般的に使用されている表現や「○○社からの提供による投稿」といった文章など。
そして、明示する方法として、主にテキスト・画像・音声・動画があります。また、近年はSNSの投稿において、関係性を明示できる機能が搭載されるようになりました。
関係性の明示にはSNS等で用いられるハッシュタグを利用して「#PR」などと表記する方法がよく使われます。ただし、「#PR」などのハッシュタグを付けていたとしても、「大量のハッシュタグの中に埋もれている」「コメントやリプライの形で記載する」といった形は不明瞭であるとして、違反になる可能性があります。
ハッシュタグの付け方などは一般社団法人クチコミマーケティング協会の「WOMJガイドライン」などが参考になります。
参考:一般社団法人クチコミマーケティング協会「WOMJガイドライン」
ステマにならないSNS投稿
ステマを疑われないSNS投稿をするには、消費者が認識しやすい形で、広告であることを明示することが重要です。事業者は、SNSごとの仕組みや機能を正しく認識した上で、投稿を依頼するインフルエンサーにも知識を共有していくことが求められます。
次ではSNSごとに、ステマを疑われないためのインフルエンサーマーケティングのポイントを紹介します。
参考:一般社団法人クチコミマーケティング協会「WOMJガイドライン」
YouTube
- 有料プロモーションの設定をオンにして、運営に申告をする。
参考:有料プロモーションの設定について - 動画内でマーケティング主体を明示する。(テロップ、企業やブランドのロゴを表記する等。)ただし、YouTubeの規定に従い動画開始から5秒以内に収める。
- ライブ配信の場合は、15分に一度ほどの頻度で、広告である旨を発言する。(「○○社の提供で配信しています」等。)難しい場合は、概要欄に記載しておく。
- ショートの場合は、タイトルに「#○○社」を記載する、もしくは動画内でロゴを掲載する。
概要欄に「提供:○○社」と記載する。
※一般視聴者にとってわかりやすいかという点を重視する場合に推奨。
- タイアップ投稿ラベルを使用する
参考:タイアップ投稿ラベルの設定について - キャプションの先頭に、関係性の明示のための「#PR #○○社」などを表記する。
※文章が長文で折りたたまれた際でも、表記が見えるようにする - ライブ配信の場合は、15分に一度ほどの頻度で、広告である旨を発言する。(「○○社の提供で配信しています」等。)難しい場合は、概要欄に「#PR #○○社」と記載する。
TikTok
- コンテンツの情報開示設定をオンにする。
参考:コンテンツの情報開示設定について - キャプションの先頭に、関係性の明示のための「#PR #○○社」を表記する。
※文章が長文で折りたたまれた際でも、表記が見えるようにする。 - ライブ配信の場合は、15分に一度ほどの頻度で、広告である旨を発言する。(「○○社の提供で配信しています」等。)難しい場合は、概要欄に「#PR #○○社」と記載しておく。
X(旧Twitter)
- テキスト記入欄、動画などのコンテンツ内において、「#PR #○○社」といったハッシュタグの表記や、関係性明示の文章を記載する。
※引用やツリーでの記載は避ける
※X(旧Twitter)では、指定された関係性明示機能はありません。
Twitch
- ブランドコンテンツ開示ツールを使用する
参考:ブランドコンテンツ開示ツールの設定について - 配信画面で、マーケティング主体のロゴを掲載する。難しい場合は、15分に一度ほどの頻度で、広告である旨を発言する。(「○○社の提供で配信しています」等。)
インフルエンサー起用時の注意点
上記のように、インフルエンサーによる不当表示は広告主である企業側の違反となるため、企業はインフルエンサー起用時にこれまで以上に注意を払う必要があります。
例えば、「広告」「宣伝」「PR」といった表記がなされていても、小さく書かれていて一般消費者が広告か否か判断できないなど不明瞭な場合も不当表示に該当します。その他にも、SNSで無数のハッシュタグの中に「#PR」の文言を紛れ込ませるといったケースも不当表示とみなされるので注意しましょう。
インフルエンサーの起用にはステマ以外にも、企業のブランドイメージと合っていないなどいくつかのリスクが伴います。以下の記事ではインフルエンサー起用による炎上にフォーカスして、詳しい対策などが紹介されています。
<あわせて読みたい>
まとめ
インフルエンサーマーケティングは、各インフルエンサーとの契約毎に運用についての説明を行う必要があります。一部の大手企業では、社内のソーシャルメディア運用ガイドラインにインフルエンサー活用時のガイドラインを策定しているケースや、インフルエンサーに特化した運用ガイドラインを定めているケースもあります。
インフルエンサーマーケティングはリスクがあるから実施しない方が良いというわけではありません。消費者に大きな影響力を有するインフルエンサーを活用することは企業の有効なプロモーション施策にもなり得るでしょう。効果を最大限に発揮させるためにも、実行の際は起用のリスクの理解と対策を万全にすることが重要です。
インフルエンサーのデジタルリスク対策はエルテスへ
関連情報
〇関連資料
・CM・広告の6つの炎上パターンから学ぶ批判のポイントと対策
・SNS含むWebデータを活用したリスクマネジメント取り組み事例7選
・インフルエンサー起用による炎上を防ぐ。リスクのポイントと対策とは?